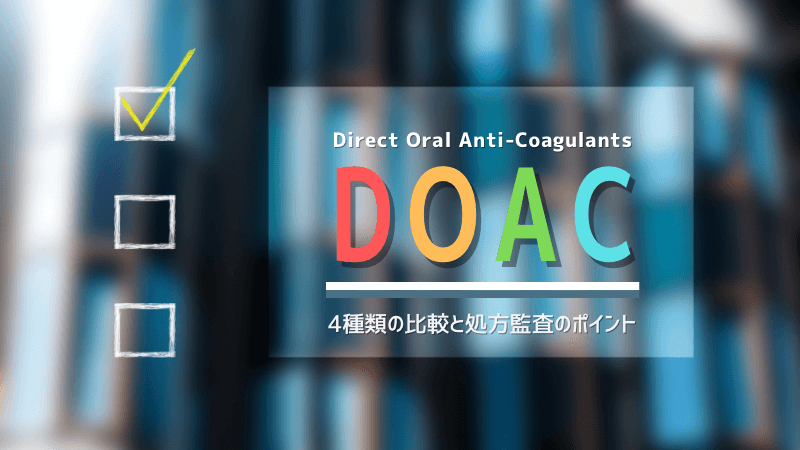今回のテーマはDOAC!
直接作用型経口抗凝固薬(Direct Oral Anti-Coagulants)の略ですね。発売当初はNOAC(Novel Oral Anti-Coagulant:新規経口抗凝固薬)と呼ばれていました。
現在、国内で使用できるDOACは全部で4種類あります。
| 製品名 | 一般名 | 発売日 |
|---|---|---|
| プラザキサ | ダビガトラン | 2011年3月 |
| イグザレルト | リバーロキサバン | 2012年4月 |
| リクシアナ | エドキサバン | 2011年7月 |
| エリキュース | アピキサバン | 2013年2月 |
DOACは処方監査が大変!
ですよね。投与の可否、投与量の減量基準、相互作用等、チェックすべき項目がいくつもあるからです。特に、減量基準。薬剤ごとに確認項目が違うだけでなく適応によって対応も変わります。
ややこしすぎて、覚えられないばかりか、以前思い込みで判断を誤りそうになったこともあります。
知識を整理しないと危ない!
そう思い、4種類のDOACについて処方監査項目の比較表を作成しました。また、どのような手順で処方監査を行えばいいのか、ポイントをまとめたので共有したいと思います。
抗凝固薬DOAC:4種類の比較

処方監査に必要な項目は何か?
添付文書の端から端まで色々とありますが、今回は薬剤ごとに内容が異なる5項目をピックアップしました。
- 適応症
- 用法用量
- 禁忌・減量基準
- 肝機能障害患者への対応
- 相互作用
抗凝固薬DOACの比較表は以下のようになります。
令和7年2月、リクシアナに慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)の効能効果が追加されました。
| 製品名 | プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | ダビガトラン | リバーロキサバン | エドキサバン | アピキサバン | |
| 剤型 | Cap | 錠・OD錠・細粒・DS | 錠・OD錠 | 錠 | |
| 規格 | 75mg/110mg | 2.5mg/10mg/15mg/DS51.7mg/DS103.4mg | 15mg/30mg/60mg | 2.5mg/5mg | |
| 適応 | NVAF | ||||
| VTE | |||||
| VTE予防 | 60mg適応なし | ||||
| CTEPH | |||||
| PAD | 2.5mgのみ | ||||
| 禁忌 | NVAF | Ccr30未満 (mL/min) | Ccr15未満 (mL/min) | ||
| VTE | Ccr30未満 (mL/min) | Ccr15未満 (mL/min) | Ccr30未満 (mL/min) | ||
| VTE予防 | Ccr30未満 (mL/min) | ||||
| CTEPH | Ccr15未満 (mL/min) | ||||
| PAD | eGFR15未満 (mL/min/1.73m2) | ||||
| 用法用量 | NVAF | 150mg×2 | 15mg×1 | 60mg×1 60kg未満 30mg×1 | 5mg×2 |
| VTE | 15mg×1 開始3週間 15mg×2 | 60mg×1 60kg未満 30mg×1 | 5mg×2 開始1週間 10mg×2 | ||
| VTE予防 | 30mg×1 | ||||
| CTEPH | 60mg×1 60kg未満 30mg×1 | ||||
| PAD | 2.5mg×2 | ||||
| 減量基準 | NVAF | 下記該当 Ccr30-50 70歳以上 消化管出血既往 110mg×2を考慮 | Ccr15-49 10mg×1 | Ccr15-50 30mg×1 出血リスク大 15mg×1を考慮 | 下記2つ該当 Cre1.5以上 年齢80歳以上 体重60kg以下 2.5mg×2 |
| VTE | 減量基準なし | Ccr15-50 30mg×1 | 減量基準なし | ||
| VTE予防 | Ccr30-50 15mg×1を考慮 | ||||
| CTEPH | Ccr15-50 30mg×1 | ||||
| PAD | 減量基準なし 2.5mg錠のみ | ||||
| 肝機能障害 | 中等度以上 禁忌 | ||||
| 代謝酵素 | P-gp | P-gp CYP3A4 | P-gp | P-gp CYP3A4 | |
| 併用禁忌 | P-gp阻害 イトラコナゾール | P-gp+CYP阻害 HIVプロテアーゼ阻害薬、アゾール系抗真菌薬(一部)、エンシトレルビル CYP阻害 コビシスタット含有製剤 | |||
| 併用注意 | 薬効重複 | 抗凝固薬,抗血小板薬,NSAIDs,SSRI,SNRI,血栓溶解剤 | 抗凝固薬,抗血小板薬,NSAIDs,SSRI,SNRI,血栓溶解剤 | 抗凝固薬,抗血小板薬,NSAIDs,SSRI,SNRI,血栓溶解剤 | 抗凝固薬,抗血小板薬,NSAIDs,SSRI,血栓溶解剤,デフィブロチドナトリウム、レカネマブ |
| 代謝酵素重複 | P-gp誘導 リファンピシン、カルバマゼピン、セイヨウオトギリソウ P-gp阻害 クラリスロマイシン | P-gp+CYP誘導 リファンピシン、フェニトイン カルバマゼピン、フェノバルビタール、セイヨウオトギリソウ | P-gp±CYP阻害 クラリスロマイシン、エリスロマイシン、フルコナゾール、ナプロキセン、ジルチアゼム、エンシトレルビルフマル酸 P-gp+CYP誘導 リファンピシン、フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、セイヨウオトギリソウ | ||
| 減量または減量を考慮 | P-gp阻害 アミオダロン、キニジン、タクロリムス、シクロスポリン、リトナビル、ネルフィナビル、サキナビル、グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル配合剤 110mg×2へ減量考慮 ベラパミル 110mg×2へ減量考慮(同時開始またはベラパミル追加時、併用3日間はプラザキサを2時間以上前に投与) | CYP阻害 フルコナゾール、ホスフルコナゾール P-gp+CYP阻害 クラリスロマイシン、エリスロマイシン 原則、VTE初期3週間は併用を避ける(NVAF・VTE維持・体重30kg以上の小児VTEは10mg×1への減量を考慮) 2.5mg錠は併用薬に関する減量基準設定なし | P-gp阻害 キニジン、ベラパミル、エリスロマイシン、シクロスポリン 30mgへ減量 (術後VTE予防は15mg減量を考慮) アジスロマイシン、クラリスロマイシン、イトラコナゾール、ジルチアゼム、アミオダロン、HIVプロテアーゼ阻害剤(リトナビル等) 30mgへ減量を考慮 (術後VTE予防は15mg減量を考慮) | P-gp+CYP阻害 アゾール系抗真菌薬(イトラコナゾール、ボリコナゾール等)、HIVプロテアーゼ阻害薬(リトナビル等) 1回量(10mg→5mg、5mg→2.5mg)の減量を考慮 | |
適応の略号
非弁膜症性心房細動:NVAF、静脈血栓塞栓症:VTE、深部静脈血栓症:DVT、肺血栓塞栓症:PE、末梢動脈疾患:PAD
見るからに煩雑ですよね。ここからは、表をもとに処方監査の手順を確認しましょう。
イグザレルトは小児に対して下記適応が認められています
静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制
Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制
抗凝固薬DOAC:処方監査の手順
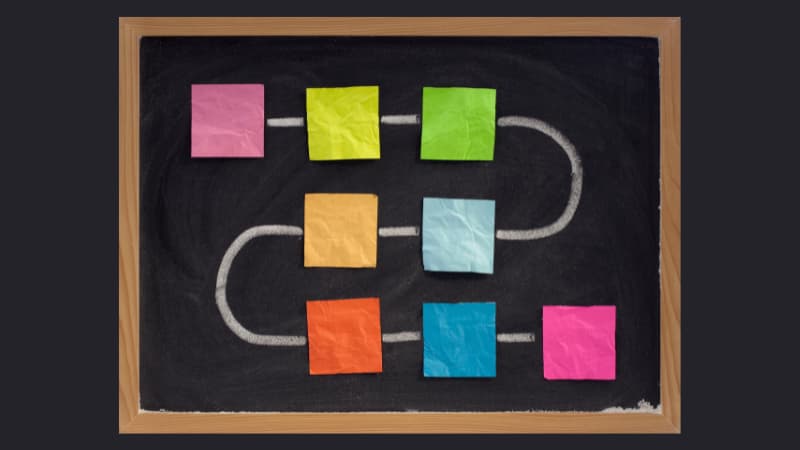
処方監査の手順は?人によって違うと思いますが、以下の手順に沿って、処方監査のポイントを解説します。
DOACの適応症
適応症のチェックは投与の可否、用法用量の妥当性を確認するために欠かせません。DOACは適応ごとに禁忌・減量基準、用法用量も異なるからです。なぜ処方されたのか?まずは処方目的を確認しましょう。
大きく4つです。
- NVAF
非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 - VTE
静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制 - 術後VTE予防
下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制(膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術) - PAD
下肢血行再建術施行後の末梢動脈疾患(PAD)患者における血栓・塞栓形成の抑制
DOAC処方監査のポイントは2つです。
- 薬剤ごとに適応が異なる
- 規格ごとに適応が異なる
順番に見ていきましょう。
薬剤ごとに適応が異なる
| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | |
|---|---|---|---|---|
| NVAF | ||||
| VTE | ||||
| 術後VTE予防 | ||||
| CTEPH | ||||
| PAD | 2.5mg錠のみ |
DOACは薬剤ごとに適応が異なります。私は以下のように頭の中を整理しています。
共通点…NVAF
相違点①…プラザキサはVTEに使えない
相違点②…リクシアナのみ術後VTE予防に使える
相違点③…イグザレルト2.5mgのみPADに適応あり
相違点④…リクシアナは慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)に適応追加(令和6年2月)
規格ごとに適応が異なる
リクシアナは適応と規格が正しいかチェックが必要になります。以下のように規格ごとに適応が違うからです。
| リクシアナ | 15mg | 30mg | 60mg |
|---|---|---|---|
| NVAF | |||
| VTE CTEPH | |||
| 術後VTE予防 | ー |
押さえておきたいのは2点です。
60mg製剤
術後VTE予防に使えない
15mg製剤
術後VTE予防のほかにも使う場面あり
ワルファリンへの切り替え時に用いる(NVAF、VTE、CTEPH)
出血ハイリスク患者に使える(NVAFのみ)
60mg製剤は術後VTE予防の適応がありません。NVAFとVTE、CTEPHのみです。30mg投与の場合は、30mg1錠または15mg2錠になります。60mg半錠は使えない点は押さえておきましょう。
15mg製剤は術後VTE予防に用いるのが基本です。当院もその目的で採用になりました。意外と知らない人が多い印象ですが、実はNVAFやVTE、CTEPHで使う場合もあります。以下のように、リクシアナをワルファリンに切り替える一定期間です。たとえば、30mg/日を投与中に腎機能が悪くなり、ワルファリン(VKA)へ変更の際には、15mgに減量(30mg製剤は半錠も可?)した上で、PT-INRが治療下限域を越えるまでVKAと併用します。
本剤からワルファリンに切り替える場合は、抗凝固作用が維持されるよう注意し、PT-INRが治療域の下限を超えるまでは、本剤30mgを投与している患者では15mg 1日1回とワルファリン、60mgを投与している患者では30mg 1日1回とワルファリンを併用投与すること。
リクシアナOD錠 電子添文
また、2021年9月にリクシアナ15mgの選択場面が増えました。高齢者(80歳以上が目安、NVAFに使用)で出血リスクが高い場合です。
下記2つの要件を満たす場合、15mgへの減量を考慮します。
リクシアナ15mgの選択基準
高齢の患者(80歳以上を目安とする)で、以下のいずれも満たす場合、治療上の有益性と出血リスクを考慮して本剤投与の適否を慎重に判断し、投与する場合には本剤15mgを1日1回経口投与することを考慮すること
次の出血性素因を1つ以上有する。
・頭蓋内、眼内、消化管等重要器官での出血の既往
・低体重(45kg以下)
・クレアチニンクリアランス15mL/min以上30mL/min未満
・非ステロイド性消炎鎮痛剤の常用
・抗血小板剤の使用本剤の通常用量又は他の経口抗凝固剤の承認用量では出血リスクのため投与できない。
リクシアナ錠 電子添文
DOACの用法用量
適応がわかったら、次は用法用量の確認です。
DOACは以下のように適応ごとに用法用量が異なります。本当に覚えるのが大変ですね。
| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | |
|---|---|---|---|---|
| NVAF | 150mg×2 | 15mg×1 | 60mg×1 60kg未満30mg | 5mg×2 |
| VTE | 15mg×1 3週間は15mg×2 | 60mg×1 60kg未満30mg | 5mg×2 1週間は10mg×2 | |
| CTEPH | 60mg×1 60kg未満30mg | |||
| 術後VTE予防 | 30mg×1 | |||
| PAD | 2.5mg×2 2.5mg錠のみ |
ポイントは2点です。
ローディングが必要
VTEの場合(イグザレルトとエリキュースのみ)
体重によって投与量が変わる
リクシアナ
VTEで用いる場合、ローディングの有無は押さえておきましょう。イグザレルトとエリキュースは一定期間、倍量投与を行います。負荷投与漏れのオーダーを何度か見たことがあるので注意が必要ですね。
リクシアナは体重の確認が欠かせません。カットオフ値は60kgです。ちなみに、体重のチェックが必要なDOACはもう一つあります。後述しますね。
DOACの腎機能チェック

続いて、腎機能チェック!
DOACは腎臓から排泄される割合が多く、腎機能に応じた投与設計が必要になります。場合によっては禁忌に該当するため、腎機能(eGFR、Ccr)のチェックが欠かせません!
プラザキサが群を抜いて高いですね。その他は大きくは変わりません(エリキュースがやや低め…)
DOACの腎機能チェック、ポイントは2つです。
- 禁忌の有無
- 減量の必要性
順番に見ていきましょう。
禁忌の有無をチェック!
まずは禁忌に該当しないか確認!ややこしいことに、DOACは薬剤ごとに禁忌の基準が異なるだけでなく、適応ごとに違います。
| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | |
|---|---|---|---|---|
| NVAF | Ccr<30 | Ccr<15 | Ccr<15 | Ccr<15 |
| VTE | Ccr<30 | Ccr<15 | Ccr<30 | |
| CTEPH | Ccr<15 | |||
| 術後VTE予防 | Ccr<30 | |||
| PAD | eGFR<15 (mL/min/1.73m2)2.5mg錠のみ |
カットオフ値は15か30です。私は適応ごとに以下のように覚えています。
- NVAF
腎排泄率の程度で区別(高率のプラザキサはCcr30未満、他はCcr15未満で禁忌) - VTE
負荷投与の有無で区別(倍量のイグザレルトとエリキュースCcr30未満、リクシアナはCcr15未満で禁忌) - 術後VTE予防
Ccr30未満(術後出血リスクに配慮して?) - PAD
腎機能の評価ツールと単位が違う(CcrとeGFR、個別と標準)
プラザキサは先述のように、尿中排泄率が高く、Ccr30未満の人には使えません。ここは絶対に見落とさないように!過去にブルーレターが発出された薬なので、特に注意ですね。
VTEの場合、リクシアナはCcr15までなら使えます。ここはポイント。腎機能が悪くエリキュースやイグザレルトが禁忌にあたる場合の代替薬になります。
eGFRとCcrどちら用いるか?
結論はどちらでもOKです。
添付文書はCcrの記載ですが、CKD診療ガイド2012によれば、「Ccr別投与量」は「GFR別投与量」とみなしてよいとされています。

減量基準をチェック!
禁忌に当てはまらないことを確認できたら、次は減量基準の確認です。
| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | |
|---|---|---|---|---|
| NVAF | Ccr30-50 70歳以上 消化管出血既往 | Ccr15-49 | Ccr15-50 | 下記2項目該当 Cre1.5以上 年齢80歳以上 体重60kg以下 |
| VTE | 減量基準なし | Ccr15-50 | 減量基準なし | |
| CTEPH | Ccr15-50 | |||
| 術後VTE予防 | Ccr30-50 | |||
| PAD | 減量基準なし 2.5mg錠のみ |
こちらも禁忌と同様に、薬剤・適応ごとに減量基準が異なります。基準がバラバラで、覚えるの大変ですよね。
毎回、添付文書ばかり見てたら仕事が進まないので、私は以下のように知識を整理しています。
- Ccrのカットオフ値
Ccr50(エリキュースは別) - Ccr以外の項目あり
プラザキサ(年齢・既往)とエリキュース(Cre・年齢・体重) - VTE
減量基準なし(例外リクシアナ、その代わり禁忌の基準が緩い?)
減量基準は本当にややこしいので、焦らずに確実にチェックを行うことが大切です。医師から尋ねられることも多いので、ある程度は記憶しておきたいですね。
処方監査には未補正eGFR(mL/min)を用いる!
血液検査結果のeGFR値(mL/min/1.73㎡)はそのままでは使用できません。標準体型(170cm 63kg)で補正された値だからです。
投与量が適切なのか?処方監査では、腎機能の評価に未補正eGFR値を確認しましょう。求め方は以下の計算式を使います。
未補正eGFR = eGFR(mL/min/1.73㎡)× 個々の体表面積/1.73㎡
詳しくは別記事にまとめているのでご確認くださいね。
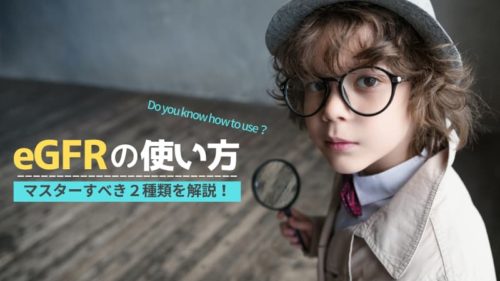
DOACの肝機能チェック
| 肝機能障害 | プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース |
|---|---|---|---|---|
| 重度 | 禁忌 | |||
| 中等度 | 禁忌 | |||
| 軽度 |
意外と盲点かも知れません。イグザレルトのみ中等度以上(Child-Pugh分類B又はCに相当)の肝機能障害患者は禁忌になります。以下のように、出血リスクが増大する可能性があるからです。
中等度の肝障害のある肝硬変患者(Child-Pugh分類B 8例)では健康被験者と比較してAUCが2.3倍上昇した。なお、非結合型のAUCは2.6倍上昇した。第Ⅹa因子活性阻害率は2.6倍増加し、PT(秒)も2.1倍延長した。Child-Pugh分類Cの患者における検討は実施していない
イグザレルトOD錠電子添文
Child-Pugh分類は肝機能障害の重症度を評価するためのもの。以下の項目からスコアを計算します。

正直言って、院外処方の場合、評価するのは難しいですよね。検査値はともかく、脳症や腹水は画像やカルテ所見を見ないとわからないから。だからといって、確認しないわけにはいかないので、患者さんに肝臓が悪いと言われたことがあるか、探りを入れてみるのはいいかも知れません。
ほかのDOACは肝機能による薬物動態への影響は問題ありません
- エリキュース…Child-Pugh分類A又はBの患者→健康成人と薬物動態は類似
- プラザキサ…中等度の肝機能障害患者→ 健康被験者とAUC0-∞は同程度
- リクシアナ…軽度及び中等度の肝機能障害患者→ 健康成人と薬物動態に大きな差異なし
※各種、添付文書より
DOACの相互作用

最後に相互作用のチェック!
DOACは併用薬剤・服薬歴のチェックが欠かせません。以下のように、薬物代謝酵素やトランスポーターの影響を受けるからです。
| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | |
|---|---|---|---|---|
| 代謝酵素 | CYP3A4 | CYP3A4 | ||
| トランスポーター | P糖蛋白 | P糖蛋白 | P糖蛋白 | P糖蛋白 |
確認手順は以下の2つのステップで考えるとわかりやすいです。
プラザキサとイグザレルトは禁忌の設定があります。
イトラコナゾール
HIVプロテアーゼ阻害剤
リトナビル(ノービア)、ロピナビル・リトナビル(カレトラ)、アタザナビル(レイアタッツ)、ダルナビル(プリジスタ、プリジスタナイーブ)、ホスアンプレナビル(レクシヴァ)、ニルマトレルビル・リトナビル(パキロビッド)
コビシスタットを含有する製剤
ゲンボイヤ、プレジコビックス、シムツーザ
アゾール系抗真菌剤(経口又は注射剤)
イトラコナゾール(イトリゾール)、ボリコナゾール(ブイフェンド)、ミコナゾール(フロリード)、ポサコナゾール(ノクサフィル)、ケトコナゾール(国内未発売)
エンシトレルビル(ゾコーバ)
いずれも血中濃度上昇により出血リスクが高まります。

該当時は併用薬の中止または変更を提案ですね
併用薬の変更が難しい場合には、どうすればいいのか?他のDOAC(リクシアナやエリキュース等)への変更が選択肢になります。
併用注意は大きく2つのパターンに分けて考えるとわかりやすいです。
- 薬効重複
- 代謝酵素の重複
①まずは薬効重複!
これはイメージしやすいのではないでしょうか。抗血小板薬なんて真っ先に思い浮かびますよね。
- 抗血小板薬
- 抗凝固薬
- 血栓溶解剤
- NSAIDs
- SSRI、SNRI
しかし、意外なものもあります。まあ、NSAIDsはなんとなくわかりますが、SSRI、SNRIにも血小板抑制作用があるそうです。セロトニンの取り込み阻害により、血小板内の5-HTが減るのが機序とされています。セロトニンは血管収縮と血小板凝集が起こすからですね。
薬効重複は4種類のDOACに共通です。



該当時は服薬後のフォローですね
(禁忌ではないので処方可です)
NSAIDsは疼痛評価により中止や他剤への変更を検討するのもありですね。
②続いて、代謝酵素の重複!
添付文書にはいろいろと書いています。ざっとみた感じ、特に多いのはイグザレルト、それにエリキュースが続きます。CYP3A4の影響を受けるからですね。



該当時は①服薬後のフォローまたは②減量の必要性を検討です
薬効重複と同様に服薬後のフォローを行うことになりますが、実は減量基準が設定されているものがあります。以下は要チェックです。
2.5mg錠は併用薬に関する減量基準が設定されておりません



プラザキサとベラパミルは併用のケースが多く、対応は覚えておいた方がいいと思います。問題になるのは、ベラパミルを一緒に開始、又は追加するときです。
逆にいうと、ベラパミルを先に服用(3日間)しており、プラザキサを追加する場合には問題になりません。減量を考慮するだけでOK。アドヒアランスを考えて、他のDOACに変更するのもありですね(←この対応は結構多い)
イグザレルトの方は、記事を書くにあたり知りました。VTE初期3週間は原則避けなければありません。他のDOACに変えるにしても、減量が必要な場合があります。



リクシアナはP糖タンパク阻害薬との相互作用に注意です。併用薬によって【減量】又は【減量を考慮】のように対応が変わる点は押さえておきましょう。
エリキュースはイグザレルトと同様に、CYP3A4、P糖タンパクの影響を受けます。イグザレルトが禁忌であるアゾール系抗真菌薬とHIVプロテアーゼ阻害薬に使用できますが、1回量の減量が必要です。
ざっとこんな感じです。DOACの相互作用はかなり多く、減量の対応が必要なものもあるので、しっかりと確認する習慣を身につけたいですね
まとめ
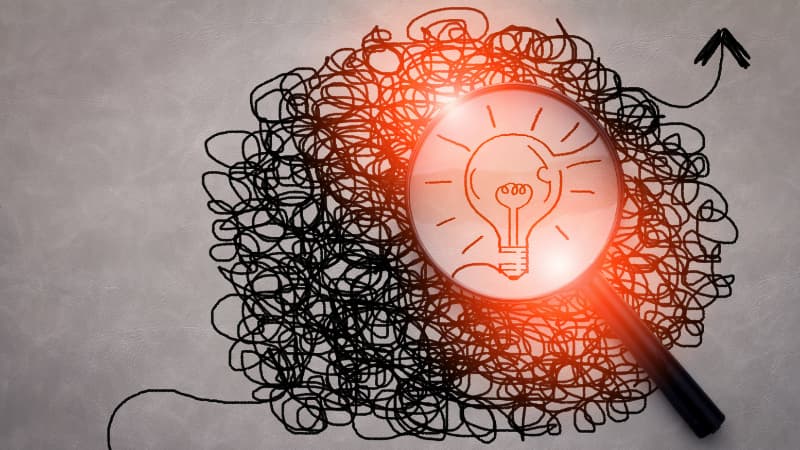
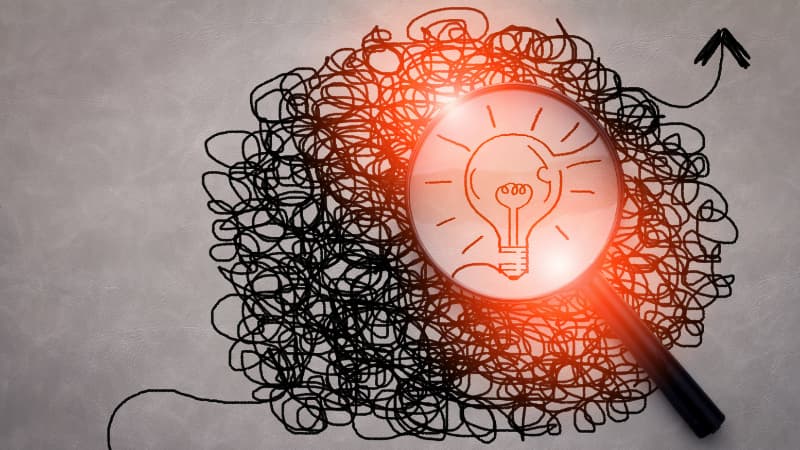
今回は、4種類のDOACを比較しながら、処方監査のポイントを解説しました。
記事を書きながら改めて思ったのは
処方監査を強化すべき点!
DOACは適応や腎機能、併用薬等によって減量基準が異なるからです。
比較表を作りながら、煩雑さを実感し、今まで確認が不十分だった点にも気がつきました。これを機に手順を見直したいと思います。
最後に、ご存知のとおりDOACはハイリスク薬剤です。処方監査のミスが思わぬ事態へと発展する危険性を秘めています。処方監査の強化により安全使用に努めましょう♪