今回のテーマはサムスカ!
一般名はトルバプタン、バソプレシンV-2受容体拮抗薬です。利尿作用のキレがよく、従来の利尿剤では効果が不十分だった例にも有効性が期待できます。
2010年に「心不全における体液貯留」の適応が承認、2013年には「肝硬変における体液貯留」、2014年には「常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制」に適応が追加されました。
2019年12月からは、OD錠も登場!今後、注射薬も発売される予定とか?!
→注射薬サムタスも発売されました!
参考記事
さらに、2020年6月には「抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善」の効能効果が追加承認されました。
今後、ますます処方の増加が見込まれるサムスカの特徴について、臨床的な位置付けや適正使用のポイントを交えながら解説します。
サムスカの基本的知識

ポイントは全部で6つです。
- 作用機序
- 特徴
- 適応
- 処方目的
- 有効性
- 臨床の位置付け
順番に見ていきましょう。
バソプレシンV2受容体拮抗薬
サムスカはバソプレシンV2受容体拮抗薬です
腎臓の集合管にあるバソプレシンV2受容体を選択的に阻害します。バソプレシンは下垂体後葉から分泌され、腎臓の集合管において水の再吸収を行う抗利尿ホルモンです。
- バソプレシンの作用機序は?
-
STEP血液側のV2受容体を刺激STEPcAMPを活性化STEPprotein kinaseを活性化STEPaquaporin-2をリン酸化STEP尿管腔より水再吸収
サムスカは選択的V2受容体拮抗薬。バソプレシンの働きを抑えて、水の再吸収を妨げ利尿作用を示します。
特徴
サムスカの特徴は純粋に水だけを体外へ排出する点です
ココが大きな違いですね。一方で、従来の利尿薬はNaやKなどの電解質の排泄をともないます。
従来薬の作用機序は以下のとおりです。
ループ利尿薬
- 作用点…ヘンレ係蹄上行脚
- Na、K、2Cl共輸送を阻害(Na、K排出)
サイアザイド系
- 作用点…遠位尿細管
- NaとClの共輸送を阻害(Na排出)
抗アルドステロン薬
- 作用点…アルドステロン受容体
- Naの再吸収とKの排泄を阻害(Na排出)
参考記事
いずれも、Na、Kなどの電解質を水とともに排泄します(=塩類排泄型利尿薬)一方で、サムスカはいわゆる水利尿剤といわれ、電解質の増加を伴わない利尿薬です。
電解質の乱れが少ないのサムスカのメリットですね。
適応
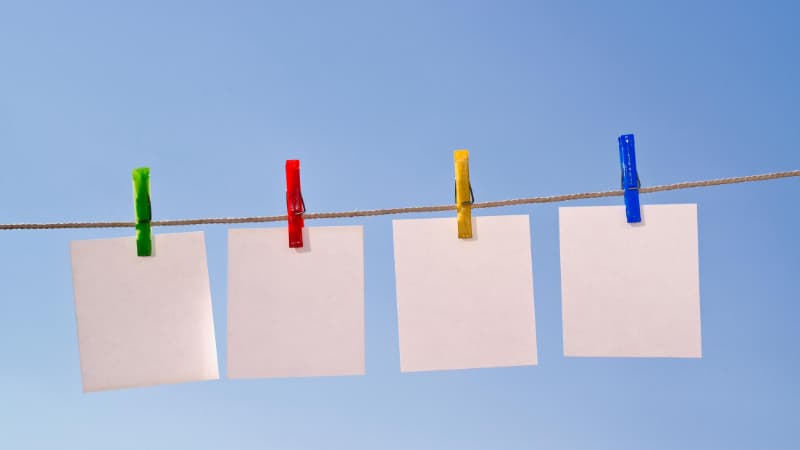
サムスカの適応は全部で4つです
冒頭で述べたように適応が次第に増えました。以下のとおりです。
ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留
ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留
腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善
日常的に良くみかけるのは心不全や肝硬変の患者さんに水分コントロールで目的で使用する場面ですね。従来の利尿薬で効果が十分に得られなときにサムスカが投与されます。
3つ目の適応は、いったいどんな病態なのか?調べてみました。
- 常染色体優性多発性嚢胞腎とは?
-
- ADPKD:Autosomal(常染色体) Dominant(優性) Polycystic(多発性嚢胞) Kidney(腎) Diseaseの略。
- 腎臓に嚢胞(袋のようなもの)ができて、次第に数が増えて大きくなる→腎臓の機能が低下していく(腎不全による透析が必要になるケースも)
- 遺伝性の疾患で、ADPKD患者数は約31,000人、約4,000人に1人が発症。
- 治療は合併症の予防と腎機能低下の進行抑制→降圧剤、水分補給、栄養管理、薬物療法
- 抗利尿ホルモンのバソプレシンは嚢胞の増殖因子→サムスカが治療に使われる
サムスカは利尿剤としての作用以外に、ADPKDの進行抑制という効果もあります。
4番目の適応もポイントを簡単にまとめたので参考にしてくださいね。
- SIADHとは?
-
- 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群の略 ※Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH(antidiuretic hormone)
- 水利尿不全による希釈性低Na血症を呈する(脱水の所見なし)
- 原因は①中枢神経系疾患、②肺疾患、③異所性バソプレシン産生腫瘍、④薬剤等
- 治療は水分制限、塩分投与、③の場合はモザバプタン
- ④はビンクリスチン、クロフィブレート、カルバマゼピン、アミトリプチン、イミプラミンなど
バゾプレシン分泌過剰症(SIADH)の診断と治療の手引き(平成22年度改訂)参照
サムスカは欧米においてSIADH患者における低ナトリウム血症の治療に係る効能・効果で承認されています。
処方目的

サムスカは何のために投与するのか?
心不全や肝硬変患者さんの場合
体液貯留の改善により、労作時の呼吸苦や倦怠感などの自覚症状を改善する
ADPKDでは、進行を抑制し透析療法を遅らせたり、合併症を防ぐために使用します。SIADHでは水分貯留や低Na血症に伴う神経症状(頭痛、倦怠感、食欲低下など)、脳浮腫などを改善するためですね。
有効性

ポイントは
短期的…心不全の兆候、自覚症状を改善する効果あり
長期的…死亡、心不全の関連事象を抑制する効果認めず
ここでは、心不全患者に対するサムスカの有効性を、短期と長期に分けて検討した試験を確認しておきますね。
海外の大規模臨床試験EVEREST
- 対象…心不全患者4133例(左室EF40%以下、心機能分類NYHA III~IV度。体液貯留を認める18歳以上)
- 方法…トルバプタン30mg/日(入院後48時間以内に標準治療に加えて最低60日間投与)
- 比較…プラセボ
- 主要評価項目…全般的臨床症状と体重の変化(7日後、早期退院の場合は退院時)
短期の有効性は?
同じ試験を2つの試験に分けて検証しました。
- trial A(トルバプタン1018例vsプラセボ1030例)
- trial B(トルバプタン1054例vsプラセボ1031例)
▽結果は以下のとおり
- 全般的臨床症状
・trial A:1.06 vs 0.99 (p<0.001 )
・trial B:1.07 vs 0.97 (p<0.001 ) - 体重の減少
・trial A:3.35kg vs 2.73kg (p<0.001 )
・trial B:3.77kg vs 2.79kg (p<0.001 )
→トルバプタンは、心不全の入院患者において短期間で心不全の兆候や症状を改善する効果が認められた
一方で、長期の有効性は?
- トルバプタン2072例vsプラセボ2061例
- 主要評価項目は①全死亡と②心血管死+心不全による入院(フォローアップ期間は平均9.9ヶ月)
▽結果は以下の通り
- 全死亡…トルバプタン群25.9%vsプラセボ26.3% HR0.98(0.87~1.11)p=0.68
- 心血管死+心不全による入院…トルバプタン群42.0% vs プラセボ40.2% HR1.04(0.95~1.14)p=0.55
→トルバプタンは長期の死亡、心不全の関連事象を抑制する効果が認められなかった
サムスカは、心不全の入院患者において短期的には臨床症状を改善しますが、長期的な予後に対する効果は認められていません。心臓保護作用のエビデンスがあるACE阻害薬やARB、β遮断薬とは位置付けが違うのですね。
海外における適応は?
米国で承認されたのは2009年。効能効果は下記です。
「心不全及び抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)等の患者における、臨床的に問題となる体液貯留型又は体液正常型の低ナトリウム血症」
同年、欧州においても「成人におけるSIADHによる低ナトリウム血症」の効能・効果で承認されています。
適応は日本と同じかと思っていたら、もともとは低Na血症の治療薬なんですね。
ガイドラインでの位置付け

心不全と肝硬変患者におけるサムスカの位置付けを確認しておきます。
心不全ガイドライン
心不全の薬物治療は以下のように分けて考えるのが一般的です。
- LVEFの低下した心不全(HFrEF)
- LVEFの保たれた心不全(HFpEF)
LVEFは左室駆出率の程度で分類されます。
- LVEFの低下した心不全…40%未満
→heart failure with reduced ejection fraction; HFrEF - LVEFの保たれた心不全…50%以上
→heart failure with preserved ejection fraction; HFpEF
HFrEF、HFpEFともに利尿剤の投与(ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬)が推奨されています。うっ血症状を改善するためですね。
では、サムスカの位置付けはどうか?
ガイドラインでは下記のとおりです。
(HFrEF)
参考文献)急性・慢性心不全診療ガイドライン2017年改訂版
・ループ利尿薬をはじめとする他の利尿薬で効果不十分な場合に,心不全における体液貯留に基づく症状の改善を目的として入院中に投与開始(Ⅱa)
(HFpEF)
・急性心不全入院中に導入されたトルバプタンを、うっ血コントロールを目的として退院後も継続投与(Ⅱa)※長期投与の有効性、安全性のデータはない
心不全のうっ血症状、治療はループ利尿薬が第一選択です。サイアザイド系などの併用も考慮します。それでも、効果が不十分な場合にサムスカを併用するのが一般的です。
サムスカは第一選択薬ではないし、入院中に導入するのが基本ですね。
肝硬変のガイドライン
下記の通りです。
①小中等量の腹水
…スピロノラクトン25〜100mg→効果不十分ではフロセミド20〜80mg併用
②大量の腹水(①で効果不十分のとき)…スピロノラクトン+フロセミド+トルバプタン
参考文献)日本消化器病学会肝硬変診療ガイドライン改訂版2015
サムスカは、他剤が効果不十分な小中等量の腹水または大量の腹水治療に使用します。もちろん、入院中の導入ですね。
サムスカの適正使用のポイント

サムスカは強力な効果が期待できる反面、安全性に配慮が必要です。
処方監査や服薬指導時に気をつけたいチェックポイントをまとめたので順に見ていきますね。ここでは、処方頻度が多い心不全と肝硬変に絞って解説します。
ポイントは大きく4つです。
- 適応と検査値の確認
- 併用薬のチェック
- 投与中の検査値モニタリング
- 脱水予防
適応と検査値の確認
適応によって投与方法が異なります。
心不全では15mg、肝硬変では7.5mgです
加えて、以下の場合には減量を考慮します
- 血清Na値…125mEq/L未満
- 急激な循環血漿量の減少が好ましくない場合
- 高齢者
- 血清Na値が正常域内で高値の場合
・血清ナトリウム濃度が125mEq/L未満の患者、急激な循環血漿量の減少が好ましくないと判断される患者、高齢者、血清ナトリウム濃度が正常域内で高値の患者に投与する場合は、半量(心不全7.5mg、※肝硬変3.75mg)から開始することが望ましい
サムスカ錠 添付文書
もちろん、禁忌もチェック!
また、高Na血症や口渇を感じない又は水分摂取が困難な患者さんは禁忌になります。高Na血症の悪化、発現リスクが高いからです。※他にも禁忌の項目があるので添付文書を確認してくださいね。
併用薬のチェック
続いて併用薬を確認します。ポイントは以下の2つです。
①CYP3A4の相互作用
②利尿薬併用の有無
CYP3A4の相互作用
サムスカは小腸または肝臓でCYP3A4により代謝を受けます。
以下の薬剤との併用時は避けるのが基本です。併用する場合には少量から、または減量を行います。
・CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、フルコナゾール、クラリスロマイシン等)との併用は避けることが望ましい。やむを得ず併用する場合は、本剤の減量あるいは低用量からの開始などを考慮すること。
サムスカ錠 添付文書
「…クラリスロマイシン等」というのが気になります。CYP3A4阻害剤は他にも色々とあるからです。とりあえず、服薬後のフォローで介入を検討するのが良いでしょうか。悩みますね。
それから、グループフルーツジュース(CYP3A4阻害)やCYP3A4誘導剤のリファンピシン 、セイヨウオトギリソウ含有食品等も併用注意です。避けること望ましいと記載があります。
サムスカ開始時と投与中は、薬物代謝酵素による相互作用のチェックが欠かせないですね。
利尿薬併用の有無
続いて、「利尿薬が併用されているか」の確認です。
ときどき、サムスカのみが処方されるケースに遭遇します。これは本当に要注意です。単独投与では高Na血症のリスクがあるからですね。
サムスカは水分だけを排出するため、血清Na値が上昇します。Naを排泄するループ系、サイアザイド系、抗アルドステロン薬となどの併用が必須です。
・本剤は水排泄を増加させるが、ナトリウム排泄を増加させないことから、他の利尿薬と併用して使用すること。
サムスカ錠 添付文書
サムスカと利尿薬の併用は意外と見落としがちなので気をつけましょう。
投与中の検査値モニタリング

続いて3つ目のポイントです。大きく2つあります。
①電解質(Na、K、Clなど)
②肝機能(AST、ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビン等)
まずは、電解質から
(心不全)
・本剤投与開始後24時間以内に水利尿効果が強く発現するため、少なくとも投与開始4〜6時間後並びに8〜12時間後に血清ナトリウム濃度を測定すること。投与開始翌日から1週間程度は毎日測定し、その後も投与を継続する場合には、適宜測定すること(肝硬変)
サムスカ添付文書
本剤投与開始後24時間以内に水利尿効果が強く発現するため、少なくとも投与開始4〜8時間後に血清ナトリウム濃度を測定すること。さらに投与開始2日後並びに3〜5日後に1回測定し、その後も投与を継続する場合には、適宜測定すること。
Na値検査のタイミングが心不全と肝硬変で異なるのがややこしいところですね。検査オーダー漏れが結構多いので、薬剤師の介入も必要だと思います。
次に、肝機能検査
(肝機能検査)
サムスカ添付文書
・本剤の投与初期から重篤な肝機能障害があらわれることがあるため、本剤投与開始前に肝機能検査を実施し、少なくとも投与開始2週間は頻回に肝機能検査を行うこと。またやむを得ず、その後も投与を継続する場合には、適宜検査を行うこと。
詰まるところ、サムスカをみたら、「電解質と肝機能は大丈夫かな?」という視点が必須ですね。
ここまでが、調剤前や処方監査時に行う最低限のチェックポイントです。続いて、服薬指導時に気をつけたい点を見ていきますね。
脱水予防

サムスカは投与中、適度な水分摂取が欠かせません
強力な利尿作用から脱水症状や高Na血症のリスクがあるからです。必ず、水分補給の必要性を伝えましょう。
一方で、過剰な水分摂取は注意!
体内貯留を促すことになりかねないので。説明時には配慮が必要です。
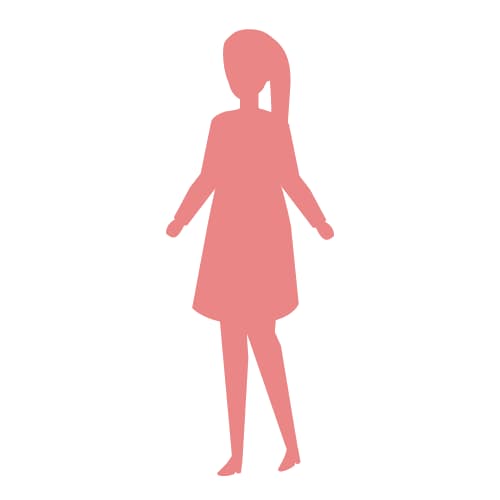 薬剤師
薬剤師サムスカ(この薬)は利尿効果が強いので、脱水症を起こす可能性があります。投与中は(のどの渇きを感じたら)水分摂取を心がけてくださいね。一方で、水分をとりすぎると胸水(や腹水)がたまりやすくなるので、飲み過ぎないように気をつけてくださいね。
たとえば、こんな感じです。
といっても、脱水予防の説明は簡単ではない!
過剰摂取にならないように、“のどの渇きを感じたら”と説明するけど、そもそも高齢者ではのどの渇きを感じにくい人も多いからです。こまめに水分補給が必要なケースもあります。ここが難しいところですね。
しかも、水分制限がある人は要注意です!
とくに、心不全の方では水分制限がある人が多いので、安易に水分摂取を促すことは適切ではありません。どのように説明するべきか医師に確認が必要です。
実際には、水分制限の範囲内で、適度に水分補給することに加えて、体重測定により基準の体重から±○kg増減があったら受診してくださいという対応が多い印象があります。
サムスカの水分管理は患者さんごとに異なるので、どのように説明すべきかを個々で検討することが大切ですね。
まとめ


ポイントは以下のとおりです。
- 分類…バソプレシンV2受容体拮抗薬
- 作用機序…集合管で水分の再吸収を妨げて水のみを排泄する
- 特徴…電解質の乱れが少なく、効果のキレがいい(従来の塩類型利尿剤と比較)
- 処方目的…心不全、肝硬変に伴う体液貯留を改善、呼吸苦や倦怠感などQOLも改善(ADPKDの進行抑制も)
- 心不全の臨床症状の改善は認められているものの、長期的な予後を改善する効果は認められてない(EVEREST)
- 心不全症状の改善にはループ利尿薬が第一選択!効果不十分の時にサムスカを使用(塩類利尿薬と併用)
- 肝硬変では軽症、中等症における他剤無効時、大量の腹水に使用(スピロノラクトン、ループ利尿薬等と併用)
- 処方チェックと脱水予防が大切。水分補給の方法、体重管理の必要性等を考慮!
今回は、バソプレシンV2受容体拮抗薬サムスカについて、臨床における位置付けと適正使用のポイントを交えながら解説しました。日常業務にお役立ていただけたら嬉しいです♪

