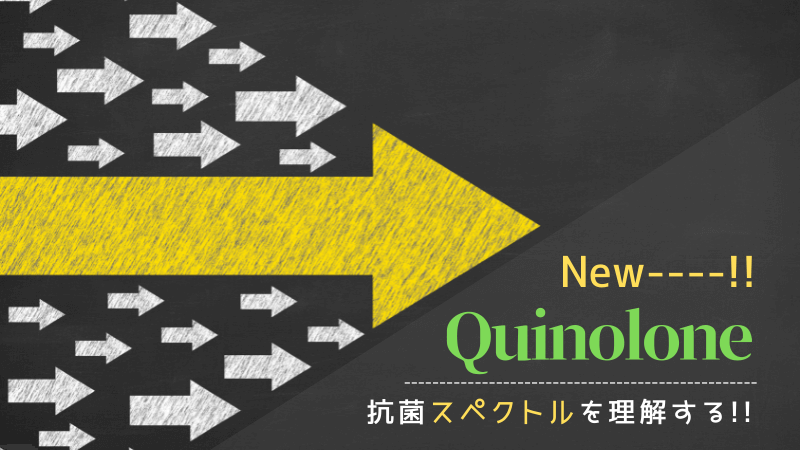抗菌薬の勉強を始めるなら、まずはペニシリンやセフェム系からですよね。
その次はどの系統を学べばいいのか?
おすすめはキノロン系!
適正使用のために押さえておきたい代表的な抗菌薬だからです
ニューキノロン系は抗菌スペクトルが広く経口投与できるのが良いところ。一方で、乱用に伴う耐性菌の問題が指摘されています。また、投与前にチェックすべき項目も少なくありません。
今回は、ニューキノロン系薬をテーマに、薬剤師が押さえておきたいポイントまとめたので共有したいと思います。
ニューキノロン系薬の基本知識
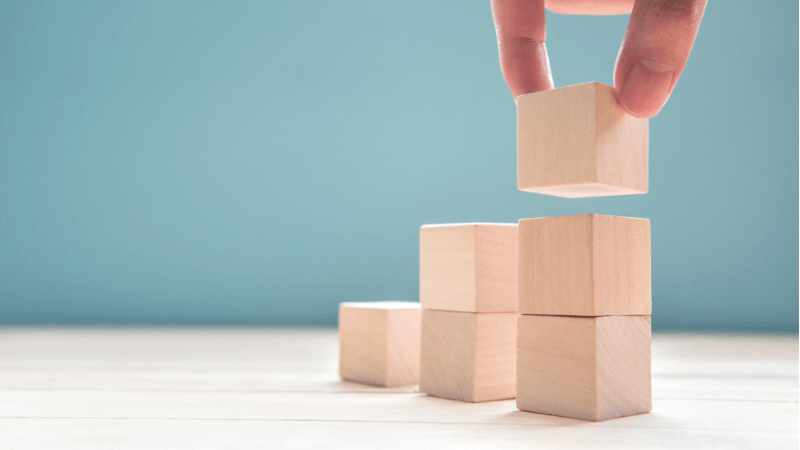
キノロン系薬の種類
まずはキノロン薬の種類から確認します。ざっと以下のとおりです。
| 略号 | 一般名 | 商品名 | 発売日 | 内服 | 注射 | 点眼 | 点耳 | 軟膏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | ナリジクス酸 | ウイントマイロン | 1964年 | 中止 | ||||
| PPA | ピぺミド酸 | ドリコール | 1978年 | 中止 | ||||
| NFLX | ノルフロキサシン | バクシダール | 1984年 | |||||
| OFLX | オフロキサシン | タリビッド | 1985年 | 眼 | ||||
| CPFX | シプロフロキサシン | シプロキサン | 1988年 | |||||
| LFLX | ロメフロキサシン | バレオン | 1990年 | |||||
| TFLX | トスフロキサシン | オゼックス | 1990年 | |||||
| SPFX | スパルフロキサシン | スパラ | 1993年 | 中止 | ||||
| LVFX | レボフロキサシン | クラビット | 2000年 | |||||
| PZFX | パズフロキサシン | パズクロス | 2002年 | |||||
| PUFX | プルリフロキサシン | スオード | 2002年 | |||||
| NDFX | ナジフロキサシン | アクアチム | 2003年 | 皮膚 | ||||
| GFLX | ガチフロキサシン | ガチフロ | 2004年 | 中止 | ||||
| MFLX | モキシフロキサシン | アベロックス | 2005年 | |||||
| GRNX | ガレノキサシン | ジェニナック | 2007年 | |||||
| STFX | シタフロキサシン | グレースビット | 2008年 | |||||
| OZNX | オゼノキサシン | ゼビアックス | 2016年 | 皮膚 | ||||
| LSFX | ラスクフロキサシン | ラスビック | 2020年 |
経口のキノロン薬は2008年以降、しばらく登場しておりませんでしたが、2019年12月にラスビック錠が承認、2020年1月に発売されました。
ニューキノロンとオールドキノロン
キノロン系薬は大きく2種類に分かれます。
- オールドキノロン
- ニューキノロン
古いか、新しいかの違いですね。ニューキノロンは、ノルフロキサシン(NFLX)以降に発売された抗菌薬です。対して、NFLX以前のキノロン系はオールドキノロンといいます。ナリジクス酸やピペミド酸などです。遠い記憶ですが、薬学部で習った気がしますね。

ニューキノロンとオールドキノロンは何が違うのか?
大きく2つです。
抗菌スペクトル
組織移行性
①オールドキノロンの抗菌スペクトルは限定的です。一部のグラム陰性桿菌のみに活性を示します。一方で、ニューキノロンは抗菌スペクトルが広いです。多くのグラム陰性桿菌に加えて、黄色ブドウ球菌やレンサ球菌などのグラム陽性球菌、マイコプラズマ(非定型細菌)、さらに嫌気性菌まで抗菌活性を有する製品も登場しています。
②オールドキノロンのナリジクス酸は組織移行性が良くありません。尿路や腸管など局所感染症のみの適応でした。対して、ニューキノロンは組織移行性が高いのが特徴です。体内動態の安定化により、高い血中濃度と組織内濃度を示し、咽頭炎や副鼻腔炎、肺炎なども含め全身の感染症に使用できます。
作用機序
キノロン系薬の作用点は2つあります。
- DNAジャイレース
- トポイソメラーゼⅣ
いずれも細菌DNAの複製に関わる酵素です。
作用点の違いにより抗菌スペクトルが変わります
①DNAジャイレースに作用…グラム陰性桿菌
②トポイソメラーゼに作用…グラム陽性球菌
従来のキノロンは①の割合が大きく主にグラム陰性桿菌に、世代の新しいキノロン系は、②の割合も高くなり、グラム陽性球菌へのスペクトル、抗菌活性が向上しています。
抗菌スペクトル
書籍によって分類方法は異なりますが、スペクトルに注目すると大きく4世代に分類できます。
第1世代
・グラム陰性桿菌(一部)
第2世代
・グラム陰性桿菌(広く)+ブドウ球菌、非定型細菌
第3世代
・第2世代+レンサ球菌(肺炎球菌を含む)
第4世代
・第3世代+嫌気性菌
第1世代のスペクトルはグラム陰性桿菌の一部です。第2世代では多くのグラム陰性桿菌やグラム陽性菌、レジオネラやマイコプラズマ、クラミジアなどの非定型細菌まで抗菌活性が広がります。第3世代以降の特徴は、肺炎球菌や溶連菌など連鎖球菌に対する抗菌力が強くなった点です。第4世代になるとバクテロイデス属やプレボテラ属など嫌気性菌に対するスペクトルが付与されます。
抗菌スペクトル表:キノロン系
世代ごとの抗菌スペクトルと対応する薬剤名は以下のとおりです。
| 世代 | スペクトル | 抗菌薬 |
|---|---|---|
| 第1世代 | グラム陰性桿菌(一部) | NA、PPA |
| 第2世代 | グラム陰性桿菌(広く) +ブドウ球菌、非定型細菌 | OFLX、CPFX、LFLX、PZFX |
| 第3世代 | 第2世代 +レンサ球菌 | TFLX、LVFX |
| 第4世代 | 第3世代 +嫌気性菌 | MFLX、GRNX、STFX |
ざっと、こんな感じです。ニューキノロン系薬の種類と対応するスペクトルはある程度、覚えておいた方がよいと思います。抗菌薬の選択やコンサルテーションで活用できる知識なので。
といっても、すべてを覚えるのは大変なので、日常良く使われる代表的なものから押さえておくのがオススメです。
・第2世代…CPFX、PZFX
・第3世代…LVFX、TFLX
・第4世代…MFLX、GRNX、STFX、LSFX
覚えておきたいのは、CPFX(シプロフロキサシン)とレスピラトリーキノロンと呼ばれるLVFX(レボフロキサシン)、MFLX(モキシフロキサシン)、GRNX(ガレノキサシン)、STFX(シタフロキサシン)の5つです。ここからは、臨床的な位置付けについて見ていきますね。
ニューキノロン系薬、臨床における位置付け
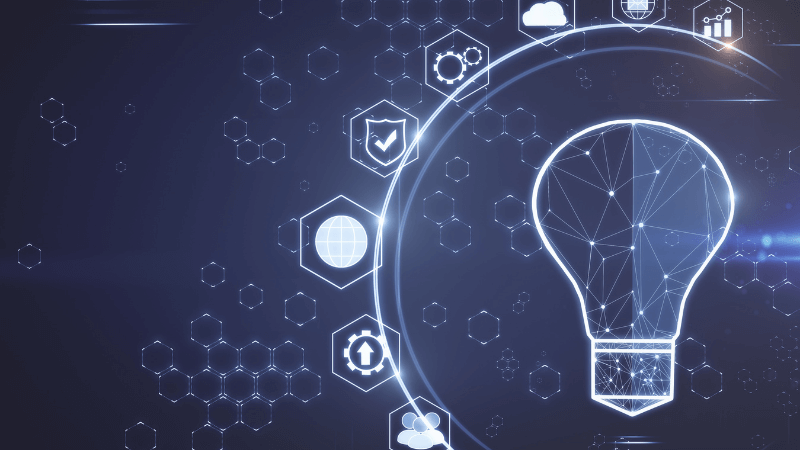
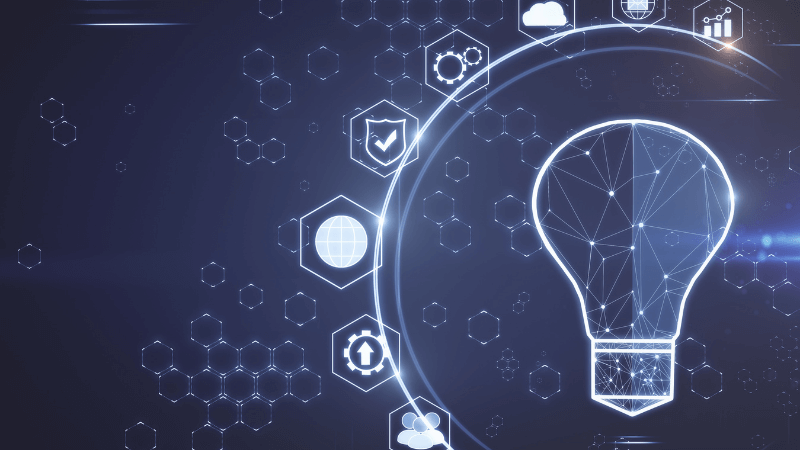
シプロフロキサシン
CPFXは緑膿菌を含めたグラム陰性桿菌の感染症に用います
第2世代のシプロフロキサシンはグラム陰性桿菌に抗菌活性が強く、中でも緑膿菌に優れているからです。たとえば、腹腔内感染症や院内肺炎などに用います。
ただし、CPFXは耐性菌防止の観点から、第一選択薬ではありません。βラクタム薬がアレルギー等で使用できない場合の代替薬という扱いです。また、嫌気性菌には効果が期待できないため、メトロニダゾール(MNZ)やクリンダマイシン(CLDM)などと併用を考慮します。
院内肺炎
敗血症があるか、重症度が高い、または耐性菌リスクがある場合:de-escalation治療
▽第二選択
・LVFX点滴静注1回500mg・1日1回
・CPFX点滴静注1回300〜400mg ・1日2回(1回400mg・1日3回まで増量可)キノロン系薬は結核菌に対する抗菌活性を有するため、使用するにあたっては結核の除外を行った上で使用する
LVFXやCPFXは嫌気性菌に対する抗菌活性が低く、使用を避けるか、CLDMまたはMNZを併用する二次性腹膜炎
市中発症(軽症〜中等症、重症)、院内発症
JAID/JSC感染症治療ガイド2023
▽β-ラクタム系薬アレルギーの場合
・CPFX点滴静注1回400mg ・1日2〜3回+MNZ点滴静注1回500mg・1日3〜4回:CPFXに替えて他のキノロン薬(LVFXなど)も使用可
一方で、レジオネラ肺炎ではキノロン系注射薬が第一選択になります。
成人細菌性肺炎、Legonella属(入院治療を原則とする)
・LVFX点滴静注1回500mg・1日1回
JAID/JSC感染症治療ガイド2023
・CPFX点滴静注1回300〜400mg ・1日2回(1回400mg・1日3回まで増量可)
・LSFX点滴静注 初日300mg・1日1回、投与2日目以降150mg・1日1回
・PZFX点滴静注1回500〜1000mg・1日2回
・AZM点滴静注1回500mg・1日1回
緑膿菌に使える数少ない経口薬の1つ
シプロフロキサシンは緑膿菌に活性がある貴重な経口薬です。たとえば、発熱性好中球減少症(FN)に対して、外来治療を行う場合に選択できます。FNは抗がん剤や免疫抑制剤の投与中に、好中球が減少し発熱を生じている状態です。緑膿菌を含めたグラム陰性桿菌、グラム陽性球菌をカバーした抗菌薬の投与が必要になります。
入院治療では、セフェピム(CFPM)やタゾバクタム/ピペラシリン(TAZ/PIPC)などを使用する一方で、外来治療が可能な低リスク例では緑膿菌に効果が期待できる経口CPFXが選択肢の一つです。ただし、グラム陽性球菌には活性が乏しく、βラクタム薬との併用療法も考慮されます。
発熱性好中球減少症
▽経口抗菌薬による経験的治療(低リスク)
保険適用外
・CPFX経口1回400mg・1日2回
・LVFX経口1回500mg・1日1回±以下のいずれか
・CVA/AMPC経口1回250mg・1日4回
JAID/JSC感染症治療ガイド2023
・CVA/AMPC経口1回250mg・1日3回+AMPC 経口1回250mg・1日3回
レスピラトリーキノロン
- TFLX(トスフロキサシン)
- LVFX(レボフロキサシン)
- MFLX(モキシフロキサシン)
- GRNX(ガレノキサシン)
- STFX(シタフロキサシン)
- LSFX(ラスクフロキサシン)
レスピラトリーキノロンは呼吸器感染症に強い!
肺炎の起炎菌、第1位は肺炎球菌!
第3世代以降のSTFX、LVFX、MFLX、GRNX、STFX、LSFXは特に肺炎球菌に活性が強いのが売りです。加えてクレブシエラやインフルエンザ菌、さらには非定型肺炎を引き起こすレジオネラやマイコプラズマなどもカバーできます。しかも、経口投与が可能で、1日1回の投与(※STFXは2〜3回/日)で済むのもメリット!
レスピラトリーキノロンは患者さんにとって利便性が良いので、特に市中肺炎の外来治療で多く用いられる抗菌薬です。
ここはポイント!
ただし、レスピラトリーキノロン薬も第一選択ではありません。
非定型細菌の関与がないと判断できれば、経口ペニシリンのクラブラン酸/アモキシシリン(CBA/AMPC)、スルタミシリン(SBTPC)などが使用できるからです。非定型細菌の可能性があっても、マクロライド系やテトラサイクリン系をまず選択します。
市中肺炎では、第二選択の位置付けです。
細菌性肺炎、非定型肺炎 外来治療
▽第二選択
参考文献)JAID/JSC感染症治療ガイド2023
・LSFX経口1回75mg・1日1回
・STFX経口1回100mg・1日1〜2回
・GRNX経口1回400mg・1日1回
・MFLX経口1回400mg・1日1回
・LVFX経口1回500mg・1日1回
・TFLX経口1回300mg・1日2回
レスピラトリーキノロンの安易な使用は、避けなければなりません。
結核菌にも抗菌活性を示すからです。一時的な症状の改善(診断の遅れ)や耐性菌の出現(治療困難)を招く可能性があります。レボフロキサシンは、リファンピシンやイソニアジドに耐性を示す結核菌に対する併用療法の選択肢の一つとして、2015年に厚生労働省が定める結核医療の基準に収載されました。
COPDなど慢性呼吸器疾患増悪時の気道感染症治療においては、原因菌すべてに優れた抗菌活性があり、臨床効果も期待できるという理由で経口キノロン薬が第一選択になっています。
▽第一選択
JAID/JSC感染症治療ガイド2023
・LSFX経口1回75mg・1日1回(抗緑膿菌作用を有さないことに注意する)
・STFX経口1回100mg・1日1〜2回
・GRNX経口1回400mg・1日1回
・MFLX経口1回400mg・1日1回
・LVFX経口1回500mg・1日1回
・TFLX経口1回300mg・1日2回
レスピラトリーキノロン6種類の特徴は
別記事に詳しくまとめていますので合わせてご覧頂けたら幸いです。
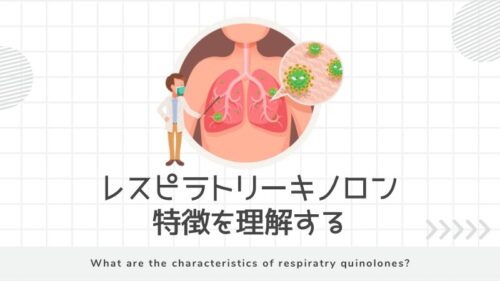
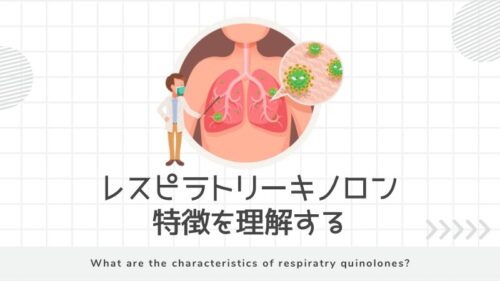
ニューキノロン系薬、処方前に確認すべきポイント
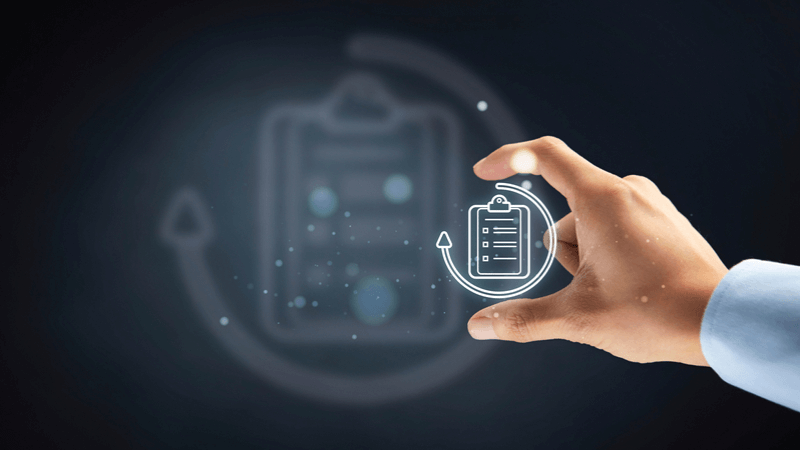
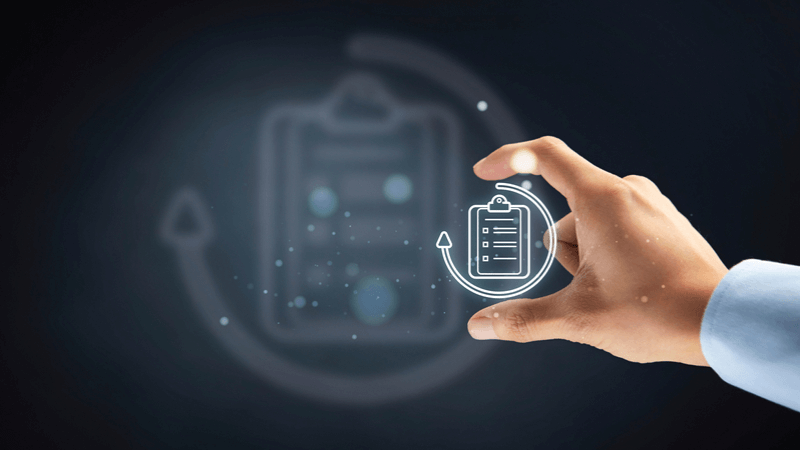
PK-PD理論
ニューキノロンは濃度依存性の抗菌薬です。
PK-PDパラメータは
AUC/MICまたはCmax/MIC
効果が1日の投与量に比例し、1日量が同じであれば、1回投与の方が高い有効性が期待できます。LVFXはもともと用法用量が1回100mg ・1日3回でしたが、有効性や耐性菌防止の観点からPK-PD理論に基づき1回500mg ・1日1回の製剤が開発された経緯があります。
MFLX、GRNXも1日1回型です。STFXはもともと1日2回でしたが、耐性菌選択のリスク低減のために、1日1回の用法が追加されました。1日2回(50mg×2)と1日1回(100mg×1)で、臨床効果が変わらないとされています。患者さんの利便性を考えると1日1回の方がよいですね。
耐性菌選択のリスク低減のために、シタフロキサシンの 1 回 100mg 1 日 1 回投与について、肺炎球菌 に対する有効性及び各種 PK-PD パラメータを、初回承認時の 1 回 50mg 1 日 2 回投与を加えた併合解析で比較検討し、両投与法に差がないことが確認できた
グレースビット インタビューフォーム
腎機能に応じた投与量
ニューキノロン薬は、ほとんどが腎臓から排泄されるからです。排泄経路ごとに分けてみると、LVFX、PZFXが腎排泄型、MFLXは胆汁排泄型。残りは、腎排泄/胆汁排泄型です。
・腎排泄型…LVFX、PZFX
・腎排泄/胆汁排泄型…CPFX、GRNX、STFX、TSFX
・胆汁排泄…MFLX
腎排泄型はもちろん、腎排泄/胆汁排泄型でも腎機能のチェックが欠かせません。高齢者やCKD、透析患者では腎機能じ合わせた投与設計が必要だからです。
一方で、胆汁排泄型のMFLXは腎機能低下例でも通常量使用できます。
排泄経路の違いは安全な薬物療法のために、処方監査や投与設計で必要な視点です。
相互作用
問題になる相互作用は、大きく4つです。
- 金属イオンとキレート形成
- CYPとの相互作用
- QT延長に注意!
- NSAIDsとの併用で痙攣
まとめると下表になります。
| CPFX | LVFX | GRNX | MFLX | STFX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属イオン | 併用注意 Al,Mg,Fe,Ca 本剤2時間後に金属 | 併用注意 Al,Mg,Fe 本剤1-2時間後に金属 | 併用注意 Al,Mg,Fe,Ca,Zn 本剤2時間後に金属 | 併用注意 Al,Mg,Fe 本剤2時間後に金属 | 併用注意 Al,Mg,Fe,Ca 本剤2時間後に金属 |
| CYP | 併用禁忌 チザニジン,ロミタピドメシル酸塩 併用注意 テオフィリンなど多数あり | ||||
| QT延長 | 併用注意 抗不整脈薬クラスⅠA、クラスⅢ | 併用注意 デラマニド | 併用注意 抗不整脈薬クラスⅠA、クラスⅢ | 併用禁忌 抗不整脈薬クラスⅠA、クラスⅢ 併用注意 エリスロマイシン,抗精神病薬,三環系抗うつ薬など多数あり | |
| NSAIDs | 併用禁忌 ケトプロフェン注射,坐薬 併用注意 フェニル酢酸系,プロピオン酸系非ステロイド性消炎鎮痛薬 | 併用注意 フェニル酢酸系,プロピオン酸系非ステロイド性消炎鎮痛薬 | 併用注意 フェニル酢酸系、プロピオン酸系非ステロイド性消炎鎮痛薬 | 併用注意 フェニル酢酸系,プロピオン酸系非ステロイド性消炎鎮痛薬 | 併用注意 フェニル酢酸系,プロピオン酸系非ステロイド性消炎鎮痛薬 |
金属イオンとキレートを形成
経口ニューキノロン薬は金属を含む製品との併用により効果が減弱します。キレート形成により吸収率が低下するからです。いずれも併用注意とされています。
(併用注意)
アルミニウム又はマグネシウム含有の制酸薬等、鉄剤・水酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、硫酸鉄等
本剤の効果が減弱されるおそれがある。これらの薬剤は本剤投与から1~2時間後に投与する。
クラビット錠、電子添文より
金属カチオンの種類はAl、MG、Fe、Ca、Znなどです。電子文書によって若干記載が異なります。対応は、「キノロン薬を先に投与し、◯時間以上空けてから金属を含む製剤を投与」です。◯にはLVFXのみ1-2、その他のキノロンは2が入ります。食間投与や金属イオンを含まない薬剤への変更等が必要ですね。
CYPとの相互作用
一部のニューキノロン薬は薬物代謝酵素CYPの影響を受けます。
特に、CPFXは注意!
筋緊張緩和剤チザニジンは併用禁忌です。CYP1A2を介した相互作用により、Cmax、AUCが大きく上昇するからです。同様に、高脂血症治療薬ロミタピドメシル酸塩ともCYP3A4を介した相互作用があり、併用禁忌の扱いになっています。
併用禁忌
チザニジン塩酸塩(テルネリン)
チザニジンのCmaxが7倍、AUCが10倍それぞれ上昇し、血圧低下、傾眠、めまい等があらわれたとの報告がある。チザニジンの作用を増強させるおそれがあるので、併用しないこと。
ロミタピドメシル酸塩(ジャクスタピッド)
ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。
シプロフロキサシン錠、電子添文
ちなみにPZFXもCYP1A2を阻害するため、テオフィリンと併用注意です。
QT延長に注意
一部のニューキノロン薬はQT延長のリスクがあります。心筋のカリウムチャネルの阻害により再分極が妨げられるからです。
特に注意すべきはMFLX
以下の抗不整脈薬との併用が禁忌です。CPFX、GRNXは併用注意とされています。
(併用禁忌)
クラスIA抗不整脈薬
- キニジン
- プロカインアミド(アミサリン)
- ジソピラミド(リスモダン)
- シベンゾリン(シベノール)
- ピルメノール(ピメノール)
クラスⅢ抗不整脈薬
- アミオダロン(アンカロン)
- ソタロール(ソタコール)等
本剤を併用した場合,相加的なQT延長がみられるおそれがあり,心室性頻拍(Torsades de pointesを含む),QT延長を起こすことがある
アベロックス、電子文書より
NSAIDsとの併用に注意
ニューキノロン薬はNSAIDsとの併用によりけいれんの誘発リスクが高くなります。中枢神経系におけるGABA受容体への結合阻害が増強されるからです。
特にCPFXは注意!
ケトプロフェン内服と注射が禁忌になります。特に注意が必要なケースは下記です。
・てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者、腎障害のある患者では特に注意すること
シプロキサン添付文書より
アセトアミノフェンへの代替を考慮!
ニューキノロン系薬に疼痛、解熱目的でNSAIDsを併用されるケースが多いので、ハイリスク例では、安全なアセトアミノフェン製剤への変更を提案することも必要だと思います。
まとめ


最後にまとめておきますね。
ポイントは以下のとおりです。
- ニューキノロンはオールドキノロンの進化版!抗菌スペクトルの拡大、移行性もアップ!
- スペクトルは4つのグループに分けて理解。新しくなるにつれて、グラム陽性球菌に強くなる。さらに非定型細菌や嫌気性菌もカバー。
- 第2世代CPFXは緑膿菌用のニューキノロン、経口投与できるのがメリット。
- 第3世代以降はレスピラトリーキノロン。呼吸器感染症の起炎菌を広くカバーしており、特に肺炎球菌に対する抗菌力が強いのが特徴です。
- ニューキノロンが第一選択になる状況はほとんどない(レジオネラ肺炎等は第一選択)。他は代替薬の位置付けで、βラクタム薬やマクロライド系薬が副作用や相互作用などで使えない時に選択する!
今回は、ニューキノロン薬をテーマに、抗菌スペクトル、臨床における位置付け、投与前のチェックポイントについて解説しました。
ニューキノロン薬はできるだけ温存しておいた方がよい抗菌薬です。薬剤耐性菌が増えて、使えない薬になるのは何としても避けるべきだと思います。