痛み止めは胃が荒れます。
医療者はもちろん、患者さんだってわかってる人が多いです。あまりにメジャー過ぎて、記事を書く必要もないんじゃない?
と思う一方で、もしかすると、実はよく知らなかったり、有名な副作用なのできちんと知識を整理しておきたい…という人もいるかも知れない?
そんな淡い期待から、今回はNSAIDsによる胃潰瘍・消化管出血リスクと予防方法についてまとめました。
NSAIDsとは?
・非ステロイド性消炎鎮痛薬の略
(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs:NSAIDs)
解熱鎮痛作用に加えて抗炎症作用を示す、ステロイドを除いた薬剤の総称です。NASAIDsは組織にあるシクロオキシゲナーゼ(COX)を阻害し、痛みや腫れの原因となるプロスタグランジン(PG)の産生を低下、炎症を鎮めます。
NSAIDsの分類
NSAIDsは大きく2種類に分類されます。
①非選択性NSAIDs
②COX-2選択的阻害薬
ターゲットとするCOX選択性の違いです。非選択性NSAIDsはCOX-1とCOX-2、どちらにも作用し、COX-2選択的阻害薬はCOX-2により選択的に作用します。
- COX-1
-
血小板や消化管、腎臓などに常時発現し、血小板の働きを強めたり、粘膜組織の血流をよくするなど生体の恒常性を維持する役割があります。
- COX-2
-
主に炎症時に誘導され、痛みや腫れを引き起こす働きです。
代表的な薬剤は以下のとおりです。
- 非選択性NSAIDs
-
- アスピリン
- ケトプロフェン
- インドメタシン
- ロキソプロフェンなど
- COX-2選択的阻害薬
-
- メロキシカム
- エトドラク
- セレコキシブなど
参考記事
NSAIDs潰瘍の機序
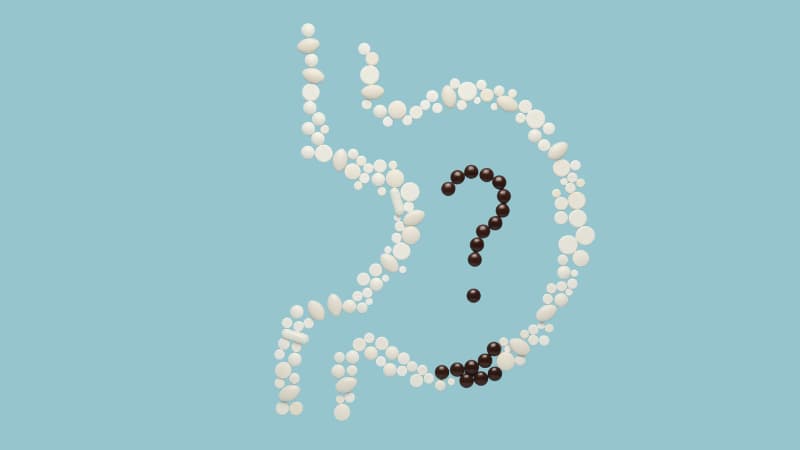
NSAIDsで胃粘膜障害が起こるのはなぜか?
PGの産生低下により、胃粘膜組織の防御機能が破綻、胃炎や潰瘍、ひどい場合には出血を引き起こすこともあります。一方で、COX-2選択的NSAIDsはCOX-1に対する作用が弱く、胃粘膜傷害が起こりにくいのが特徴です。
実はCOX-2選択的NSAIDsにも意外な盲点があります!
COX-2阻害薬は傷ついた粘膜の修復を遅延させるからです。COX-2は組織の治癒を促す作用(COX-1の代償作用)があり、COX-2阻害薬は直接的ではないにせよ胃潰瘍の発症に加担してしまいます。
NSAIDs潰瘍は2つの要因で起こるという理解です。
- COX-1阻害による粘膜障害
- COX-2阻害による組織治癒の遅延(代償作用の妨げ)
COX-1だけで粘膜障害が起こるわけではありません。傷ついた組織を修復するためにCOX-2の代償作用が働くからです。両方の阻害により、生体の恒常性が破綻すると考えられています。
COX-2選択的阻害薬を飲んでいたら安心というわけではありません。非選択的NSAIDsよりは安全性が高いですが、潰瘍リスクはゼロではないわけです。
胃潰瘍や消化管出血の頻度

NSAIDsによる胃粘膜障害はの頻度はどのくらいなのか?
3カ月以上の長期間、NSAIDsを服用している関節炎患者1008人の上部消化管障害発生率は、以下のとおりでした(リウマチ,31:96-111,1991)
- 胃炎…38.5%
- 胃潰瘍…15.5%
- 胃潰瘍瘢痕…8%
- 十二指腸潰瘍…1.9%
胃潰瘍とその瘢痕までを合わせると約25%です。
つまり、NSAIDsを長期に服用すると、10人のうち2〜3人が胃潰瘍を発症する計算です。胃炎まで含めると約6割に胃粘膜病変を認めることになります。
たしかに、手術後の疼痛管理でNSAIDsを服用している人が吐き気や食欲不振を訴えるのは稀ではないし、消化管出血で入院された人がNSAIDsを飲んでいたーーというのは日常的に目にする光景です。やはり、NSAIDsの胃粘膜障害には注意が必要なんですね。あらためて思いました。
NSAIDs潰瘍のリスク因子
- 出血潰瘍既往歴
- 消化性潰瘍既往歴
- 高用量NSAIDsやNSAIDsの併用者
- 抗凝固薬・抗血小板薬や糖質ステロイド、ビスホスホネートの併用者
- 高齢者
- 重篤な合併症を有する者
- H.pylori陽性者
この中から、以下3つのリスク因子について見ていきます。
- ピロリ菌感染
- NSAIDs(LDA)
- ビスホスホネート製剤の併用
ピロリ菌感染
NSAIDsもそうですが、ピロリ菌も独立した危険因子です。両方の因子が重なると胃潰瘍や消化管出血のリスクが倍増することがわかっています。
海外のメタ解析によれば、ピロリ菌感染(なし)・NSAIDs服用(なし)の患者における胃潰瘍と消化管出血のリスクを、それぞれ1とした場合、リスク因子の組み合わせによるオッズ比は以下のとおりでした。
- ピロリ菌(あり)・NSAIDs(なし)→胃潰瘍18.1倍 / 消化管出血1.79倍
- ピロリ菌(なし)・NSAIDs(あり)→胃潰瘍19.4倍 / 消化管出血4.85倍
- ピロリ菌(あり)・NSAIDs(あり)→胃潰瘍61.1倍 / 消化管出血6.13倍
ピロリ菌感染はNSAIDsによる胃潰瘍や消化管出血のリスクが増加させるわけですね。
ちなみに、ピロリ菌感染が認められる人は、NSAIDs投与前に除菌療法が推奨されています。前もって潰瘍のリスクを下げておくためです。一方で、もうすでにNSAIDsを飲み始めている人は、除菌療法は勧められていません。予防効果が十分ではないからです。
NSAIDs投与開始予定例では、潰瘍発生予防目的のH.pylori除菌は行うよう推奨する
【推奨の強さ:強、エビデンスレベル:A】
潰瘍治癒前は、NSAIDs服用に伴い発症した潰瘍に対するH.pylori除菌は治癒率を高めない
ピロリ菌感染↓ NSAIDs潰瘍↑
最近では、除菌療法の普及に伴いピロリ菌を起因とした胃潰瘍のリスク自体は減っているそうです。一方で、高齢化により循環器疾患や整形外科疾患を持つ人も増え、NSAIDsや低用量アスピリン(LDA)を飲む人が増加しています。
NSAIDs併用(LDA含む)
NSAIDs+LDAの処方はよく見かけます。
例えば、変形性膝関節症や関節リウマチなどの疾患で、NSAIDsを服用している人が、循環器疾患でLDAを併用する場合などですね。以下のように、LDAの併用はNSAIDs単独又はCOX-2阻害薬単独に比べて消化性潰瘍リスクが高まります。
消化管出血のリスク
*Adjusted for age, sex, calendar semester, ulcer history, nitrates, anticoagulants, antiplatelets and acid‐suppressing drugs.
†Categorised only among NSAID current single users.
LDAを併用した場合、非選択的NSAIDsとCOX-2阻害薬、どちらもリスクが増強します。胃の負担が少ないCOX-2阻害薬のメリットが相殺されてしまうわけです。
ビスホスホネート併用
高齢者ではよくある組み合わせです。経口ビスホスホネート製剤(BP)とNSAIDsとの併用リスクが指摘されています。
NSAIDsを3ヶ月以上服用している関節リウマチ患者196人を対象とした後ろ向きコホート研究によれば、内視鏡的潰瘍の発生率は以下のとおりでした。
- BP併用群…31%(21/68)
- 非併用群…17%(22/128)
→BP併用群の方が、潰瘍リスクが高い
※多変量解析調整オッズ比 2.29(1.09-4.81)
経口BP製剤は単独でも、直接粘膜を刺激して潰瘍を誘発します。NSAIDsとの併用によりさらにリスクが高まるので注意が必要です。
骨粗鬆症の患者さんの多くは、痛み止めを飲んでいます。中でもNSAIDsのケースが多く、経口BP製剤との組み合わせ処方は日常的に遭遇する、あるある処方ですよね。
胃部不快感や胃潰瘍などを認める場合はどうすればいいか?NSAIDsの中止や安全性の高いアセトアミノフェンへの変更が基本ですが、静脈内投与ができるBP製剤への変更もリスク低減のための選択肢になります。
NSAIDs潰瘍・消化管出血の予防方法

ここからは、NSAIDs潰瘍を予防するための方法を見ていきましょう。
大きく3つあります。
- 早期発見とモニタリング
- 予防薬または代替薬を提案する
- NSAIDsの必要性を評価する
早期発見とモニタリング
やっぱり副作用の兆候をいち早くキャッチして、重篤化を防ぐことが大切ですよね。まずは自覚症状の確認です。NSAIDsの処方時に事前に患者さんに説明しておくと、早期発見につながります。
- NSAIDs潰瘍の自覚症状
-
- 胃痛や吐き気
- めまいやふらつきなどの貧血症状
- 血便
- NSAIDs服用中に確認すべき検査値
-
- ヘモグロビン値(Hb)
- 尿素窒素(BUN)
- クレアチニン(Cre)
検査値の中でHbはイメージしやすいと思います。推移から消化管出血の可能性を探ることができるからです。過去に比べて低下傾向が見られたら、もしかしてNSAIDsの影響?という思考ですね。
では、BUNとCreは何か?
実は消化管出血の可能性を教えてくれます。順番に説明しますね。
まずBUNは消化管出血でも上昇します。出血した血液に含まれるタンパク質が腸管内で代謝を受けて、アンモニアを発生し、吸収後さらに代謝を受けて最終的に血中BUNを上昇させるからです。BUNの上昇は腎機能の悪化や脱水だけではないのですね。
一方で、Creは腎機能低下で上昇しますが、消化管出血による影響は受けにくい性質があります。そのため、Creと比較してBUNが高値を示すようであれば、腎障害ではなく脱水や上部消化管出血の可能性が高いと判断できるわけです。
一般的には、BUN/Cre比>30 が上部消化管出血の可能性が高いと判断する目安になります。
予防薬または代替薬を提案する
続いて2つ目です。一次予防と二次予防に分けて考えます。
潰瘍の既往がない一次予防
胃潰瘍や消化管出血を防ぐために予防薬の投与が提案されています。
NSAIDs潰瘍の発生予防は潰瘍既往歴がない患者においても必要であり、PPIによる予防を行うように提案する
【推奨の強さ:強、エビデンスレベル:A】
プロトンポンプ阻害薬(PPI)以外にも、プロスタグランジン製剤(PG)、H2拮抗薬、レバミピドなどが一次予防で有効であったとの報告があります。
いずれの薬剤もNSAIDs潰瘍の一次予防における保険適応がありません
また、COX-2選択的阻害薬を選択するのも一つです。非選択的NSAIDsよりも潰瘍発生リスクが低く、投与が推奨されています。
NSAIDs潰瘍発症の予防にCOX-2選択的阻害薬の使用を推奨する
【推奨の強さ:強、エビデンスレベル:A】
潰瘍の既往がある二次予防
NSAIDs併用下でPPIの投与が推奨、ボノプラザンの投与が提案されています。
潰瘍既往歴のある患者のNSAIDs潰瘍の予防には、PPIを推奨し、ボノプラザンを提案する
【推奨の強さ:弱、エビデンスレベル:B】
出血性潰瘍既往歴のある患者のNSAIDs出血性潰瘍の再発予防には、COX選択的阻害薬にPPI併用を推奨する
【推奨の強さ:強、エビデンスレベル:B】
ミソプロロールも投与可能ですが、下痢の副作用が多く、妊婦または妊娠の可能性のある人にも使用できないため、PPIの方が使い勝手が良いです。
また、出血を伴う潰瘍既往歴がある高リスク例では、非選択的NSAIDsではなくCOX-2選択的阻害薬とPPIの併用が推奨されています。NSAIDs自体をCOX-2阻害薬に変更してリスクを最小化する方法です。
NSAIDsは本当に必要?という視点をもつ
最後に3つ目。

痛みがあるからNSAIDsを飲んでいる……とは限りません。ここは盲点だと思います。NSAIDsの必要性が低いのに飲み続けている人は意外と多いですよね。
例えば、このような患者さん
- もうすでに痛みが治まってるのに、痛み止めを未だに処方されている人
本人もそれに気づいてない - 痛みがないのに、やめることが不安でいつまでも飲み続けてる人
そんなこと言ってたら永遠にやめられない
痛みがないのであれば、NSAIDsを投与する必要はありません。抗炎症作用を期待してる場合もあるかも知れないですが…。不要な投薬は胃潰瘍や消化管出血のリスクを増加させる危険だってあります。
NSAIDsを飲んでる人がいれば、「痛みの状態は?本当に飲まなければいけないの?」と、立ち止まって考えてみる」ことが大事です。
まとめ
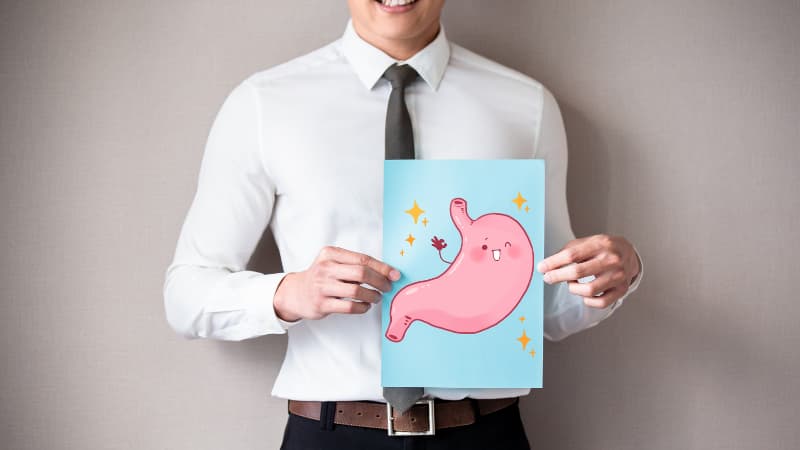
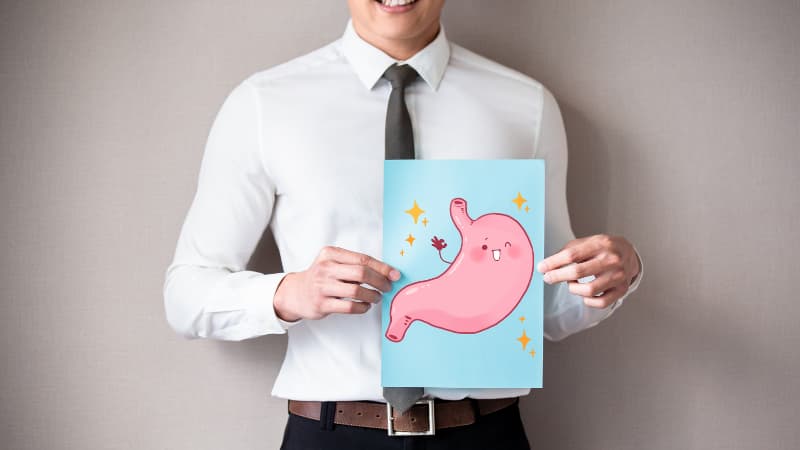
今回は「NSAIDsによる潰瘍・消化管出血」をテーマに、適正使用のポイントをあえて解説しました。
本記事のポイント
- NSAIDsの胃潰瘍・消化管出血リスク
-
- 非選択的NSAIDsよりもCOX-2選択的阻害薬の方がリスクが低い!
- NSAIDs潰瘍はCOX-1阻害による粘膜障害に加えてCOX-2阻害による治癒遅延が関与、COX-2阻害薬はノーリスクではない!
- NSAIDs潰瘍のリスク要因にピロリ菌感染、LDA・ステロイド・BP併用などがある!
- 潰瘍・消化管出血を防ぐためにできる3つの方法
-
- 自覚症状に加えてCre、BUN、Hbなど検査値のチェック!消化管出血の兆候を早期にキャッチする!
- 一次予防でも予防薬の投与が提案。二次予防では推奨。PPIの併用やCOX-2選択的阻害薬の選択を!
- 疼痛コントロールを確認!不要なNSAIDsを減らす視点を持っておきたい

