「お薬手帳があってすごく助かった!」
と、心から感謝する経験はありませんか?
私は病院薬剤師です。
最近、お薬手帳のニーズが高まっていると感じています
コロナ禍で隔離対応の患者さんが多く、また高齢化で認知機能が低下した方も増えており、直接の聞き取りが困難だからです。入院前の服薬情報を記したお薬手帳は、薬剤師にとって、宝のありかを記した地図ともいえるでしょう。
それなのに、手帳をパラパラめくって、次の瞬間、怒りが込み上げてきます!
「このお薬手帳、全然役に立たない、最悪!」
(床に叩きつけそうになる^_^笑)
役に立たないだけならまだしも、誤解を与える危険な記載もあります。
「なんとかしないと!」
そこで今回は、「お薬手帳に潜む罠」と題して、薬剤師が陥りやすい事例を紹介、解決法も考察したので共有したいと思います。
お薬手帳に潜む罠

お薬手帳に潜む罠は、大きく3つに分類できます。
- 記入漏れ
- 誤解を招く記載
- 患者さんの自己調節
おそらく、ピックアップできていないものや、私がまだ遭遇していない未知のワナもあるはずです。見つけ次第、追記したいと思います。
順番に見ていきましょう。
記入漏れ
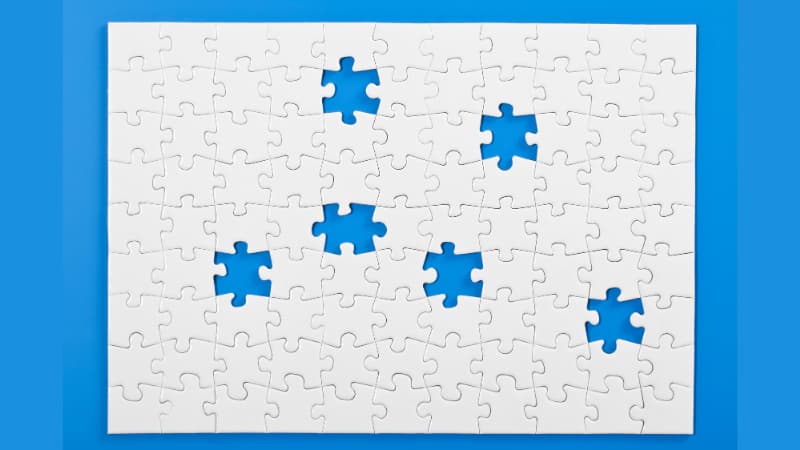
記入漏れは最もメジャーな罠ですね。
安全な薬物療法の継続に支障をきたします
薬効や投与量、相互作用のチェック等の抜けが生じるだけでなく、入院患者さんでは不完全な処方が継続されてしまう可能性があるからです。
以前、手帳に書いていないのに、近医でワルファリンの処方を受けている人がおられ、冷や汗ものでした…。
記入漏れといっても、大きく3つのパターンがあります。
- (患者さんの)シール貼り忘れ
- (医療機関が)記載せず
- 注射薬の記載がない
(患者さんの)シール貼り忘れ
患者さんのシール貼り忘れはかなり多い!
あるべき箇所に抜けが散見されるし、持参薬や情報提供書などにまぎれてヒラっと宙を舞うこともしばしばです。きちんと貼る人もおられますが、実際には紛失されたり、置き去りになっているシールが多いと思います。
もちろん、処方歴シールは医療機関で貼りますが、お薬手帳を持参されない時は自宅で貼るように患者さんにお渡ししているのが現状です。
(医療機関が)記載なし
これも未だに多いです
特に、院内処方の医院やクリニックの処方が書かれていないケースが目立ちます。
「◯◯先生のところは手帳に書いてくれない…」と愚痴をこぼす患者さんは少なくありません。
最近では、手書きやお薬の説明書きを兼ねた紙を貼ってくれる医院やクリニックも増えていますが…。
注射薬の記載がない
注射薬はほぼ見当たりませんね
おそらく、医療機関では処方というよりは処置という感覚で、お薬手帳に書くという発想自体がないからだと思います。
最近では、化学療法のレジメンは多くの病院で書かれるようになっていますが、以下の注射製剤はほぼ、記載されておりません。
| 分類 | 一般名 | 商品名 |
|---|---|---|
| ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 | デノスマブ | プラリア皮下注 |
| 骨粗鬆症治療剤 | テリパラチド酢酸塩 | テリボン皮下注用 |
| 骨粗鬆症治療剤 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | ボナロン点滴静注 |
| 骨粗鬆症治療剤 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | ボンビバ静注 |
| 骨粗鬆症治療剤 | ゾレドロン酸水和物 | リクラスト点滴静注 |
| 持続型赤血球造血刺激因子製剤 | ダルベポエチン アルファ | ネスプ注射液 |
| 持続型赤血球造血刺激因子製剤 | エポエチン ベータ ペゴル | ミルセラ注 |
| 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤 | インフリキシマブ | レミケード点滴静注 |
| ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤 | ベドリズマブ | エンタイビオ点滴静注 |
デノタスチュアブル錠の記載から、デノスマブの存在に気づくことは可能ですが、そのほかの注射薬の定期投与は見落とされているケースが多いと思います。
あと、お薬手帳を2冊で運用されている人を見かけませんか?
処方機関ごとに、手帳を分けて管理されている場合ですね。記入漏れと同じ事態が起こる可能性があります。一冊(A病院)だけを提出されると、もう片方(B医院)の存在に気づかないことがあるからです。
一つにまとめるか、同時に提出しないと危ない旨をお伝えしたのを、今思い出しました。
誤解を招く記載
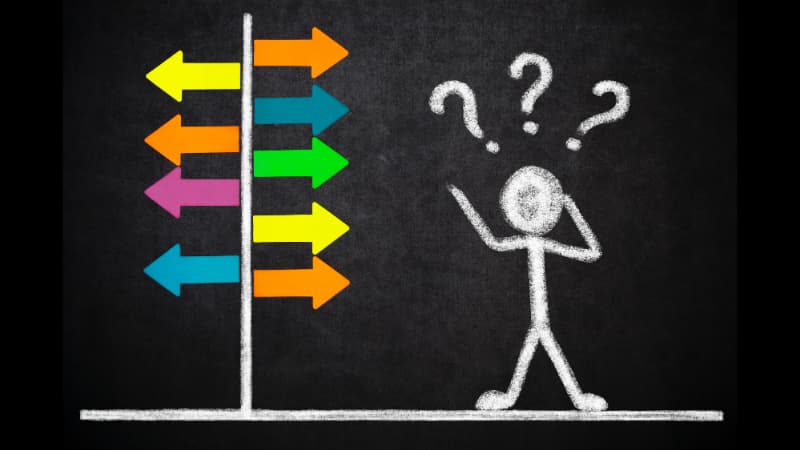
続いて2つ目の罠です。
誤解を招く記載は安全な薬物療法の妨げになります
受け取り方次第で間違った解釈が生じ、不測の事態につながる可能性があるからです。
経験から大きく2つあります。
- 残薬調整のRP→処方中止と誤認
- 中止処方→記載がない
残薬調整のRP
残薬調整は危険を秘めています
処方日数がお薬手帳の確認日まで届いてない場合には、読み手からすれば中止と解釈する危険があるからです。意外と知られていないので余計に危ないと感じています。
もちろん、処方日数が不揃いの時はなんとなくわかりますが、残薬が多く、処方日数が0日分になるRPは気づきません。
中止処方
中止薬はお薬手帳だけでは判断できません
そもそも、中止処方という概念がお薬手帳にはないからです。
「名前が消えた」=「中止」と解釈していますが、残薬調整の可能性もあるし、Aという薬が中止されて、Bに変更された場合は、お薬手帳の表記では、Bが追加されたように見えます。
前々回のシール
処方内容
調剤日3/1
- フロセミド錠20mg 1錠
分1朝食後 56日分 - Bカプセル◯mg 2cap
分2朝夕食後 56日分 - C錠◯mg 2錠
分1夕食後 56日分 - D錠◯mg 3錠
分3毎食後 56日分
前回のシール
処方内容
調剤日4/1
- フロセミド錠10mg 1錠
分1朝食後 28日分
30mg/日の増量?、10mgに減量?
患者さんの自己調節
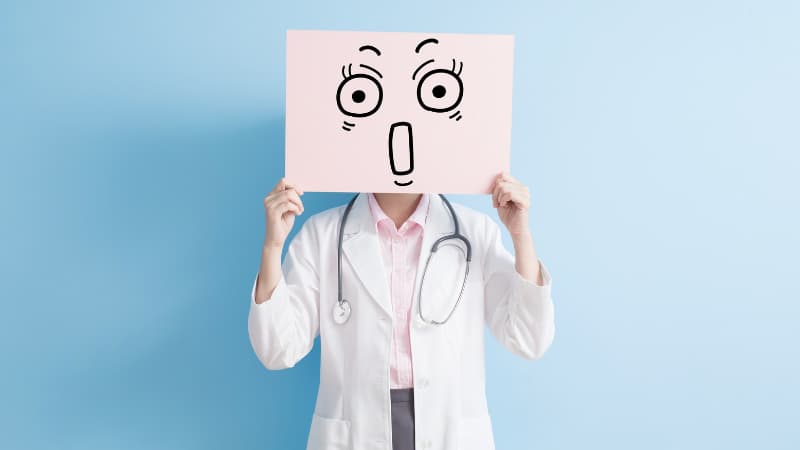
最後に3つ目の罠。
これは盲点といえるかも知れません
お薬手帳に処方歴の漏れがなくても、処方の変更や残薬調整などの形跡がなくても、患者さんが自己調節している可能性が残されているからです。
下記の2パターンはよく見かけます。
- 飲んでいない
- 用法・用量を変えている
飲んでいない
大量の持参薬を見ている薬剤師なら共感できると思います。「薬局より在庫あるやん!」って心の叫びが表に出ている人は少なくありませんよね笑
「処方」=「飲んでいる」ではないのです
それに気づかないと、誤った薬効評価や処方提案に繋がり、患者さんを危険に晒す可能性もあります。
用法・用量を変えている
用法の自己調節も多いです。よくあるのは下記でしょうか?
- 朝食後昼食後(朝ごはんを食べないから)
- 分3分1〜2(副作用を心配して)
- 外出時は帰宅時に飲む(利尿剤)
- 透析日の前日は飲まない(刺激性下剤)
- 連日隔日投与(検査値が良くなってるから)
ある程度、許容できるものから、対応が必要なものまで様々ですね。
また、用量の自己調節もよく見かけます。
特に睡眠薬。眠れないから、2錠飲んだり、副作用を心配して0.5錠に減らしたりと。もう好きにやってますよね笑
肝に銘じておくべきは、
「お薬手帳の用法用量」=「実際の飲み方」とは限らないこと
ズレに気づかないと、入院前の服薬状況を無視することになります。以前、「いつもと飲み方が違う」と不満を訴えられる患者さんがおられました。また、服薬アドヒアランス改善に対する介入の機会も失われます。
お薬手帳を扱う、書き手と読み手の心得

では、どうすれば罠に引っ掛からずに、お薬手帳を安全に活用できるのか?
結論をいうと

お薬手帳を扱う、「書き手」と「読み手」の心がけ次第だと思います。
書き手は読み手の求める情報を考える
お薬手帳になぜ処方歴シールを貼るのか?
安全な薬物療法を担保するために必要な情報だからですよね。
つまり、情報を受け取る相手がいるわけです。それなら、読み手がどのような情報を求めているのかを考えるべきだと思います。
読み手が欲しい情報は大きく2つです
- 現在の投薬情報
- 処方変更や追加の理由
現在の投薬状況
読み手からすれば把握した情報をできるだけ書いて欲しいです。
特に、聞き取った併用薬の情報。
もし仮に記入漏れ、シールの貼り忘れがあっても補うことができます。
あと、地味にビスホスホネート製剤の服用日
を書いてくれているのはありがたいです。一方で、抗がん剤のレジメンや注射薬等を書くのは病院薬剤師の役割ですね。
処方変更や追加の理由
読み手は増量や減量、追加等の理由を求めています。
誤った解釈を防ぐことができるからです。
あと、残薬調節(特に0日分)の旨
欲を言えば、疑義照会の内容も
必要に応じて書いてくれたら、助かります。
とにかく、自分が書いて欲しい情報は、相手も欲しいはずです
もちろん、むやみやたらに書けばいいわけではないですが、必要性が高いと判断できるものは、できるだけ書く心がけが大切だと思います。
読み手は細心の注意を払う


一方で、読み手はどうすれば?
罠が潜んでいる可能性を忘れず、慎重に情報を受け取らなければなりません。
先述のように、お薬手帳の記載は現在の服薬歴とズレている可能性があるからです。
そういえば、最近もありました!
- 手帳に書いてない糖尿病薬を実は飲んでいた人
- 主治医と内内に投与方法や用量を変更している人
- お薬手帳を2冊!?持ってるのに1冊だけ提出した人
気づかないと、不完全な情報をもとに処方の継続がされ、患者さんに不利益を与える可能性があります。
とにかく
「お薬手帳の記載」≠「実際の服薬状況」である可能性
は肝に銘じておくことが大切です。お薬手帳と患者さんからの聞き取り内容の答え合わせは必須だと思います。
ただし、それができないケースが増えているのが悩ましいところ…。
薬局と病院の連携が大事!


お薬手帳が不完全な要素を含むのは、今後も変わらないと思います。そもそも、持参されなければ活用もできないわけだし…。
となると



「病院」と「かかりつけ薬局」との連携が重要になります!
なぜなら、入院患者さんの服薬情報を安全かつ円滑に把握できるからです。
たとえば、お薬手帳がなくて、服薬情報の把握に行き詰まった時でも、かかりつけ薬局の名称がわかれば、視界がパッと開けます。わざわざ罠の可能性があるお薬手帳から、リスクを冒してまで情報を集めなくても、正確な情報が手に入るからです。難しい問題の糸口を見つけたような感覚ですね。
今までも、何度も助けて頂きました。本当に感謝です。
ただし、ときどき残念なケースもあります。
「うちの薬局は、A病院からの処方箋を受けていますが、他にかかっている医療機関の情報まではわかりません」って言われることもあるからです。
ここは、お互い課題だと思います
病院薬剤師も退院された患者さんのことを聞かれたら、入院中の処方について自信を持って答えられるようになりたいので。
お薬手帳を通じての間接的な情報共有に加えて、薬局と病院との直接の連携を補完すれば、完璧だと思います!ちょっと言い過ぎですかね笑
まとめ


今回は、お薬手帳に潜むワナ、よくある事例とその解決法を紹介&考察しました。
罠(ワナ)は減らせますが、なくなりません。
でも、罠がわかれば回避は可能です!
(わからないから罠にハマるので…)
解決法は
「罠を知り、罠を仕掛けない」こと
読み手側は過信せず、細心の注意を払いながら情報を受け取らなければならないし、書き手は誤解を与える可能性がないか、不足情報がないかを考える必要があるからです。
お薬手帳は安全な薬物療法に欠かせないもの。でも、結局は使い方次第だと思います。患者さんに不利益がないようにお互いが気をつけましょう。あと連携も大事ですね♪

